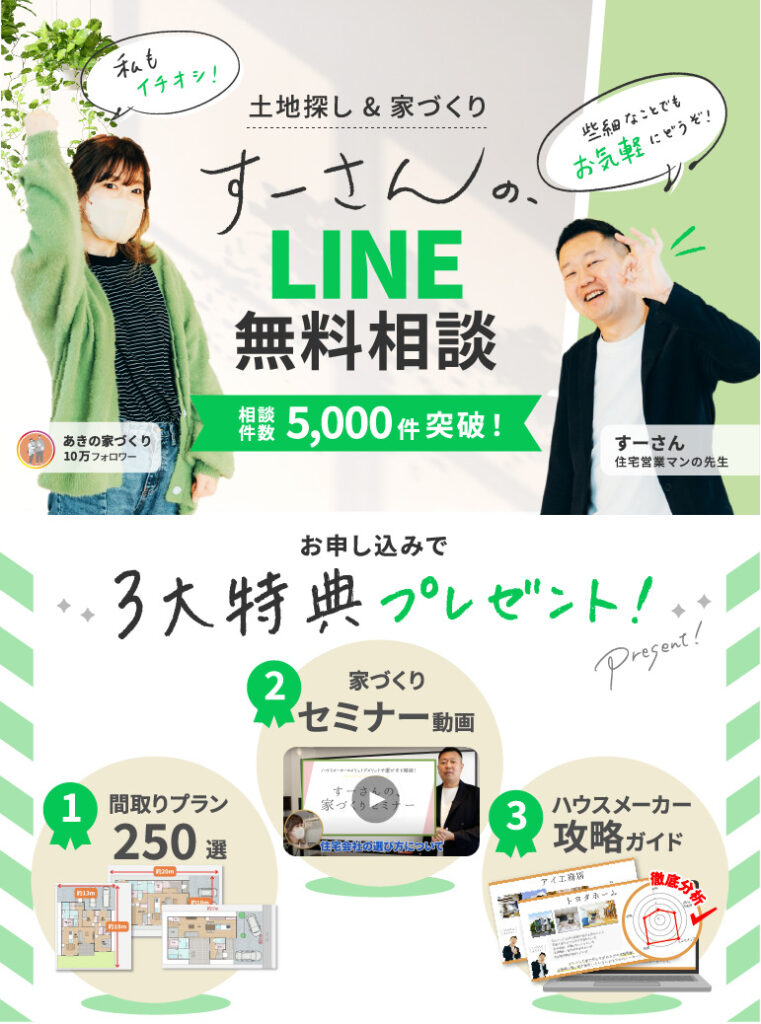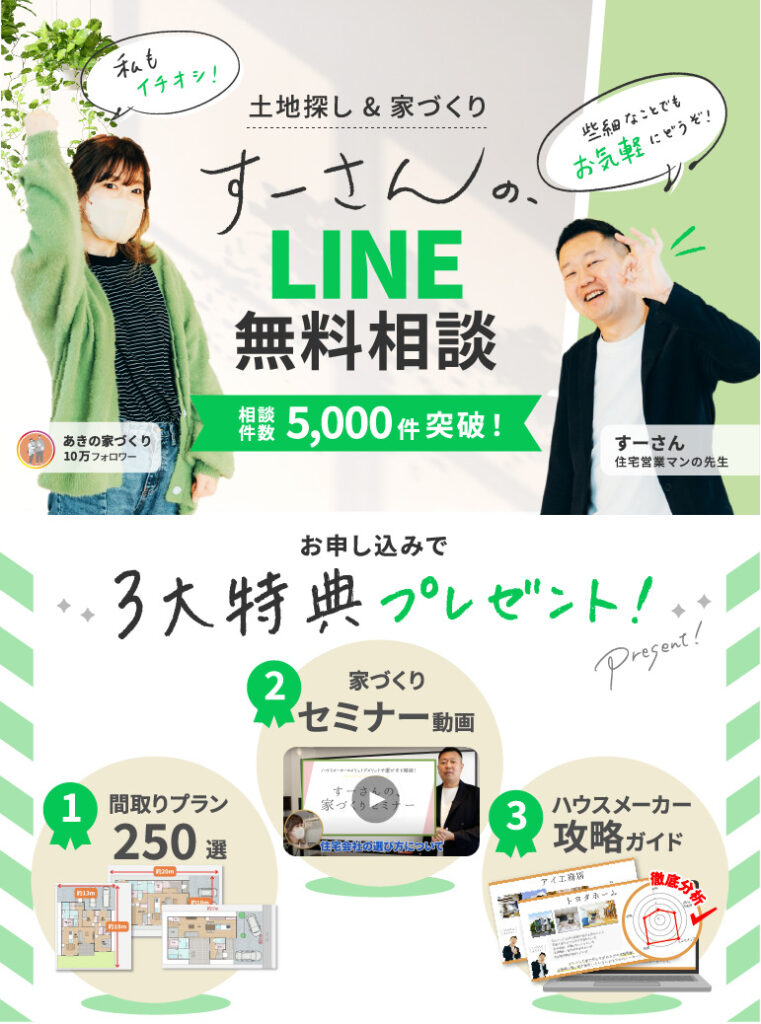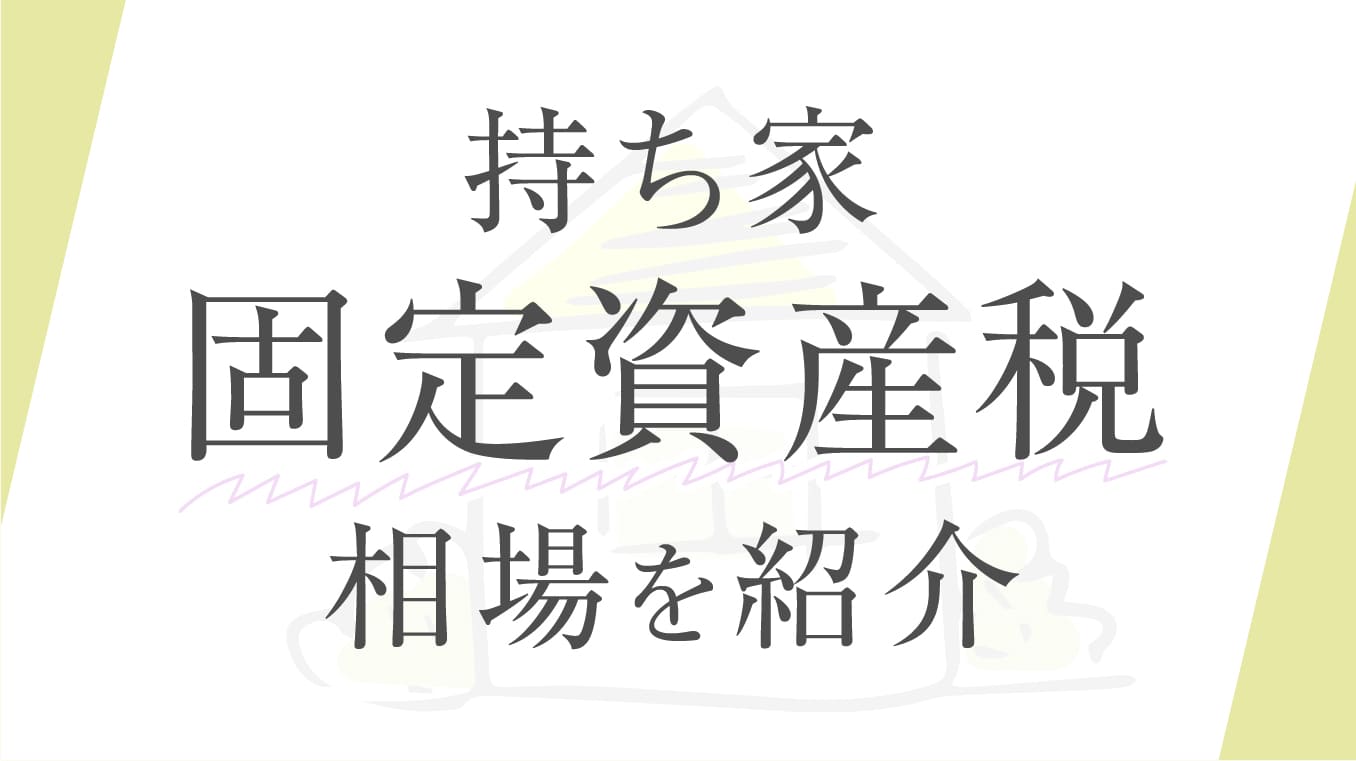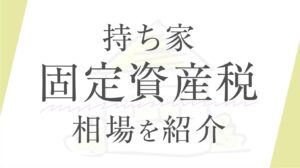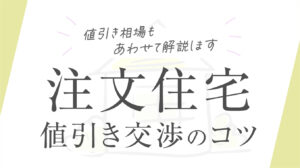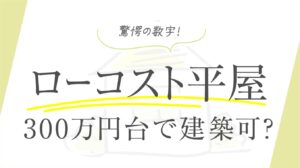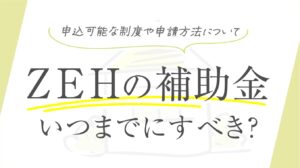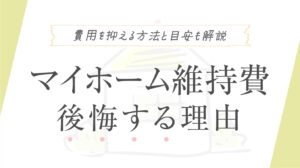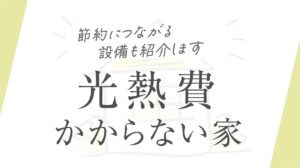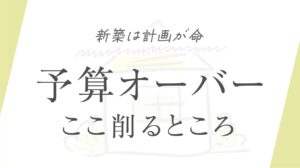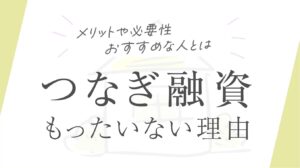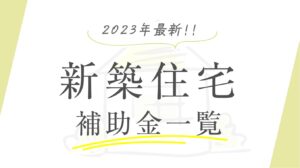「持ち家の固定資産税はいくら?」
「持ち家を買いたいけど、税金が高いならマンションにしたほうがお得?」
「できるだけ安く持ち家を購入したい!」
持ち家の固定資産税は、年間で10〜15万円が平均です。持ち家の固定資産税を減らして、生活費や趣味にお金を使いたいという方もいるのではないでしょうか。
固定資産税を減らすためには、分筆登記したり、クレジットカードで支払いしたりすることが重要です。
この記事では、持ち家の固定資産税を節税する方法について、家づくりのプロである筆者が以下の内容を紹介します。
- 固定資産税の計算方法
- 市街化区域内の税金
- 軽減措置が適用される場合
- 固定資産税を節約する方法
- マンションと税金が異なる理由
- 税金の支払時期と方法
 すーさん
すーさん初心者の方にもわかりやすく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください!
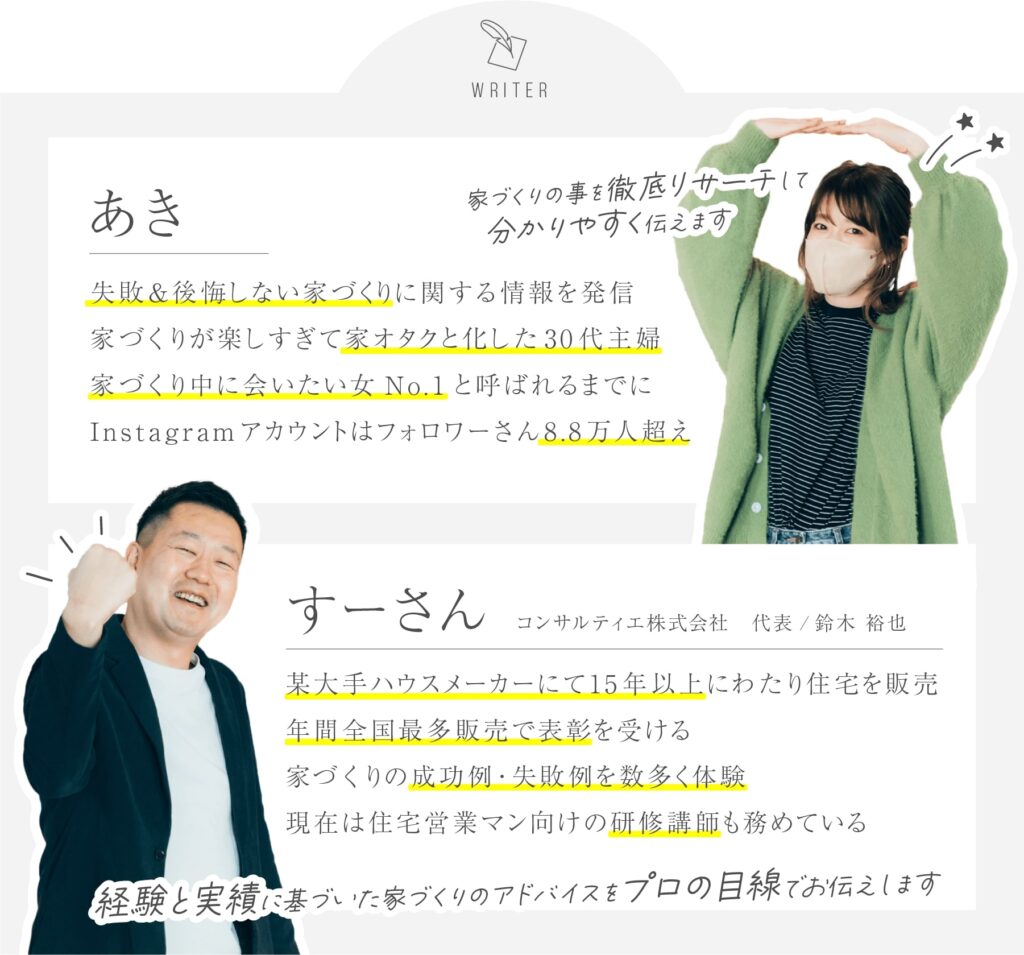
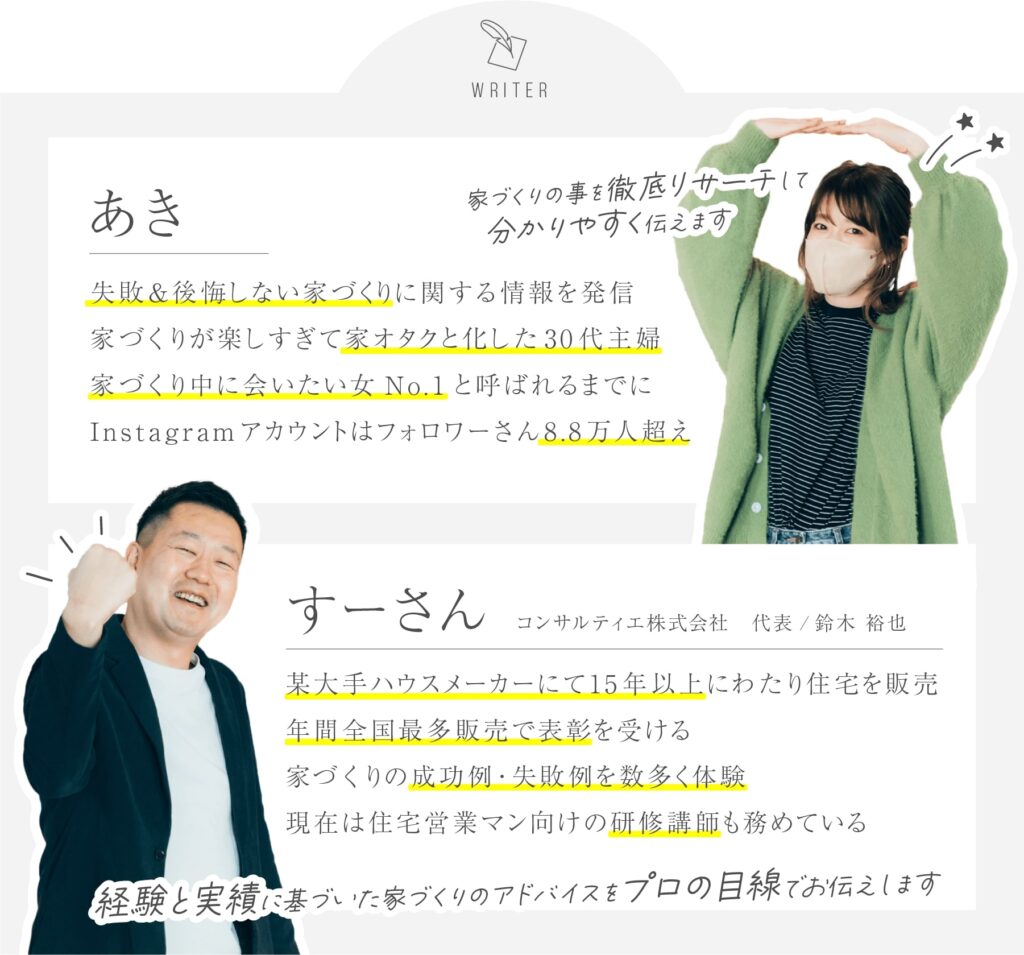
持ち家の固定資産税の年間平均は10~15万円


持ち家の固定資産税は年間10〜15万円が平均ですが、以下の条件によっても変動します。
- 住宅の種類・構造
- 築年数
- 立地エリア
一戸建てかマンションかで固定資産税が大きく異なるため、事前に調べておくことが大切です。都心部は固定資産税も上がりやすく、新築であるほど高いお金を払わなければなりません。



年間平均が10〜15万円なので、多くの家庭は月1万円以上支払う必要があります!
なお、固定資産税以外にも毎月かかる費用については、関連記事「【事前に確認】マイホームに毎月かかる5つのお金!総額の目安や節約する方法を解説」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!


持ち家の固定資産税はいくら?計算方法をシミュレーションで解説


持ち家の固定資産税額は、建物と土地を別々に計算して、合算した金額になります。それぞれの固定資産税は「固定資産税評価額(課税標準)×標準税率1.4%」で算出できます。
「固定資産税評価額(課税標準)」とは、税額を決める際の基準となる評価額です。土地や建物によって評価額は大きく異なります。そのため、固定資産税額を計算する際には、まず自身の物件の「評価額」を確認する必要があります。
また「標準税率」とは、地方税法で定められた標準的な数字です。市町村は財政上の理由などから、標準税率を参考に税率を独自で決められるため、自身の物件のある自治体の税率を確認しておくことが必要です。
ここでは、以下のように具体的なシミュレーションをしていきます。
- 土地の固定資産税の計算方法
- 建物の固定資産税の計算方法
1つずつ確認していきましょう。
1. 土地の固定資産税の計算方法
土地の固定資産税評価額(課税標準)は、市区町村窓口で発行してもらえる「固定資産税評価証明書」で確認できます。
これから取得する方は、土地取引の基準となる「公示価格」の70%の金額を固定資産税評価額の目安にしましょう。公示価格は国土交通省が毎年3月に発表しており「標準地・基準地検索システム」で確認可能です。
なお、公示価格3,000万円の土地の場合には「固定資産税評価額」及び「固定資産税額」は、以下のとおり算出できます。
- 固定資産税評価額 3,000万円×70%=2,100万円
- 固定資産税額 2,100万円×1.4%(標準税率)=29.4万円



住宅用の土地は面積の軽減措置が適用されるため、実際の固定資産税評価額は引き下がります。
2. 建物の固定資産税の計算方法
建物の固定資産税評価額(課税標準)も土地と同様に、市区町村で受け取れる「固定資産税評価証明書」で確認できます。
これから家を建てる方は、建築費用の50~60%を固定資産税評価額の目安とすると良いでしょう。
例として、建築費2,000万円の家の場合には「固定資産税評価額」及び「固定資産税額」は、以下のとおり算出されます。
- 固定資産税評価額 2,000万円×50%=1,000万円
- 固定資産税額 1,000万円×1.4%(標準税率)=14万円



新築の場合には、引き渡しから3年間は固定資産税評価額が1/2になる軽減措置があります!
市街化区域内では固定資産税とあわせて都市計画税も徴収される


固定資産税の負担額を把握する際には、都市計画税についてもあわせて確認しておきましょう。土地計画税とは、都市計画法で市街化区域と定められているエリアにある土地と建物に対して課税される税金です。
市街化区域は、市区町村が公表している都市計画図で確認できます。



不動産会社であれば市街化区域の範囲を把握しているので、土地の購入前に確認しておきましょう!
固定資産税と同様に、毎年1月1日時点で所有している方に課税されます。
なお、都市計画税の計算式は「固定資産税評価額(土地+建物)×0.3%」です。住宅用地の場合、土地の固定資産税評価額には「200㎡以下の部分は1/3」「200㎡超の部分は2/3」となる軽減措置があります。
年数が経つと建物の固定資産税は減額する


建物は劣化により価値が下がるため、年数が経てば「固定資産税評価額(課税標準)」は引き下がります。
経年劣化による固定資産税評価は「経年減点補正率」という数値を用いて計算される仕組みです。経年減点補正率については、以下の表を参照してください。
| 経過年数 | 経年減点補正率 |
|---|---|
| 1年 | 0.80 |
| 5年 | 0.64 |
| 10年 | 0.50 |
| 15年 | 0.37 |
| 20年 | 0.25 |
| 25年 | 0.21 |
表を見ると1年経過で固定資産税評価額は80%となり、25年で経年減点補正率の下限である20%近くまで下がります。



なお、土地は建物とは違い「古くなる」という概念がないため、経年によって固定資産税額が減るということはありません!
より詳しい固定資産税のシミュレーションや将来のライフプランを決めたい方は、すーさんの相談窓口の活用がおすすめです。元ハウスメーカーで15年間営業をしていた家づくりのプロに、なんでも質問できます。



一人ひとりに適したアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください!
\ ノープランでOK /
固定資産税の軽減措置が適用される4つの対象物


住宅や住宅用地の固定資産税は、軽減措置を活用すれば引き下げられます。固定資産税の軽減措置は、市区町村への申請が必要です。



申告をしなければ、過大に固定資産税を支払わなければならないため、注意が必要です。
こちらでは、以下の4つの不動産に対する軽減措置を解説します。
- 住宅用地
- 新築住宅
- 改修工事をした住宅
- 認定長期優良住宅
固定資産税を節税するために、一つずつ押さえておきましょう。
1. 住宅用地
住宅用地には、固定資産税評価額が「200㎡以下の部分は1/3」「200㎡超の部分は2/3」となる軽減措置があります。例えば、固定資産税額2,100万円の500㎡の住宅用地では、土地を以下の2つに分けて計算します。
- 小規模住宅用地:面積200㎡・固定資産税評価額840万円
- 一般住宅用地:面積300㎡・固定資産税評価額1,260万円
次に、それぞれに標準税率1.4%をかけて合算し税率を掛けると、固定資産税額が求められます。
- 固定資産税評価額:(840万円×1/6)+(1,260万円×1/3)=560万円
- 固定資産税額:560万円×1.4%=約7.8万円



軽減措置を受けなかった場合には29.4万円であったため、約21万円も税金が引き下がりました!
持ち家の土地面積を考えるときは、固定資産税が減額される範囲を覚えておきましょう。
2. 新築住宅
新築住宅で以下の要件を満たしている物件は、引き渡しから3年間、固定資産税の金額が半分に減額されます。
- 2026年3月31日(令和8年)までに新築された住宅
- 住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
- 併用住宅の場合は居住部分の割合が1/2以上
- 一戸建て以外の貸家住宅は、一戸につき40㎡以上280㎡以下



固定資産税額が1,000万円の家の場合、毎年14万円の税金が3年間1/2になるため21万円の減税ができます。
また、新築の固定資産税半額の措置は、マンションの場合でも適用されます。減額措置を受けられる期間は、戸建てよりも長い5年間です。長期的な目で見れば木造一戸建て住宅のほうが安い固定資産税になりますが、最初はマンションのほうが減額される期間が長いのが特徴です。



どちらがいいのかしっかり考えなければなりませんね!
3. 改修工事をした住宅
バリアフリーや耐震工事などの改修工事をした住宅は、固定資産税が減額されます。軽減措置の期間は、2026年3月31日(令和8年)までです。
税金が減額されるのは工事を行った翌年のみなので、長期的な効果はありません。減額割合は、以下の通りです。
- 耐震リフォーム:固定資産税の1/2
- バリアフリーリフォーム:固定資産税の1/3
- 省エネリフォーム:固定資産税の1/3
- 長期優良住宅化リフォーム:固定資産税の2/3
申請には、以下の要件を満たす必要があります。
- 耐震リフォーム: 対象工事費用50万円超、1982年1月1日以前から存在する家屋であることなど
- バリアフリーリフォーム:対象工事費用50万円超、65歳以上の要支援認定を受けているかが居住しているなど
- 省エネリフォーム:高性能給湯器・冷暖房機への交換、ソーラーパネルの設置など
- 長期優良住宅化リフォーム:耐震改修工事または省エネ改修工事を行い長期優良住宅の認定を受ける
継続的に固定資産税を減額させたいなら、木造一戸建て住宅を購入して、定期的にリフォームするのがおすすめです。



固定資産税減額のために改修工事をするなら、あらかじめ条件を確認しておきましょう!
4. 認定長期優良住宅
長期優良住宅とは、長期間・良好な状態で暮らせるように設計された住宅のことです。省エネ住宅やZEH住宅を新築すると、認定を受けられます。要件は、以下のとおりです。
- 令和8年3月31日までに建築・購入すること
- 住宅の延床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 長期優良住宅認定通知書を取得していること
長期優良住宅に認定されると、固定資産税だけではなく、所得税や登録免許税も減税されます。長期優良住宅を新築した場合は、5年間物件の固定資産税が半分になるので、引き渡してからしばらくはお得に感じられるでしょう。



環境に配慮した住宅を建てると、軽減措置が適用されます!
認定を受けられる住宅については、関連記事「【迷いを払拭】マイホーム購入のメリット・デメリット12選!賃貸との比較や向いている人の特徴も紹介」で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください!
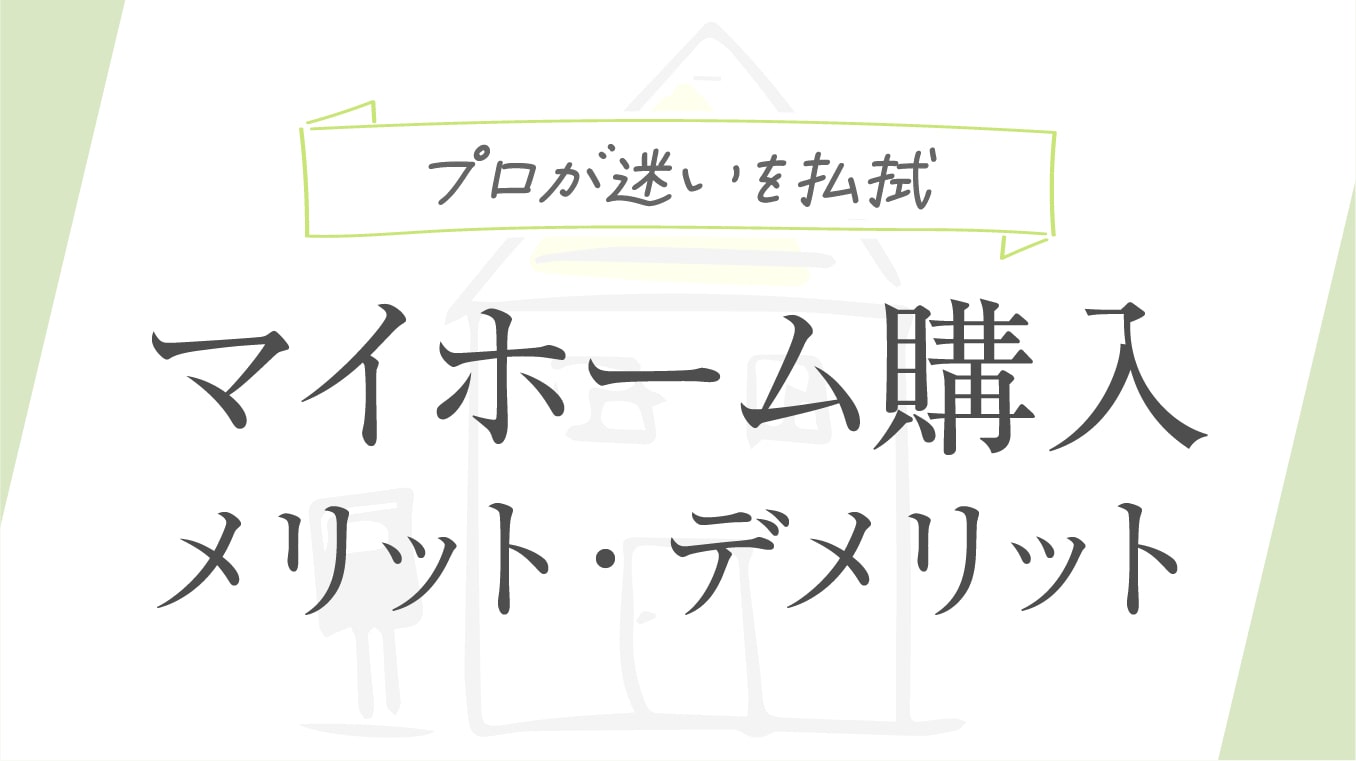
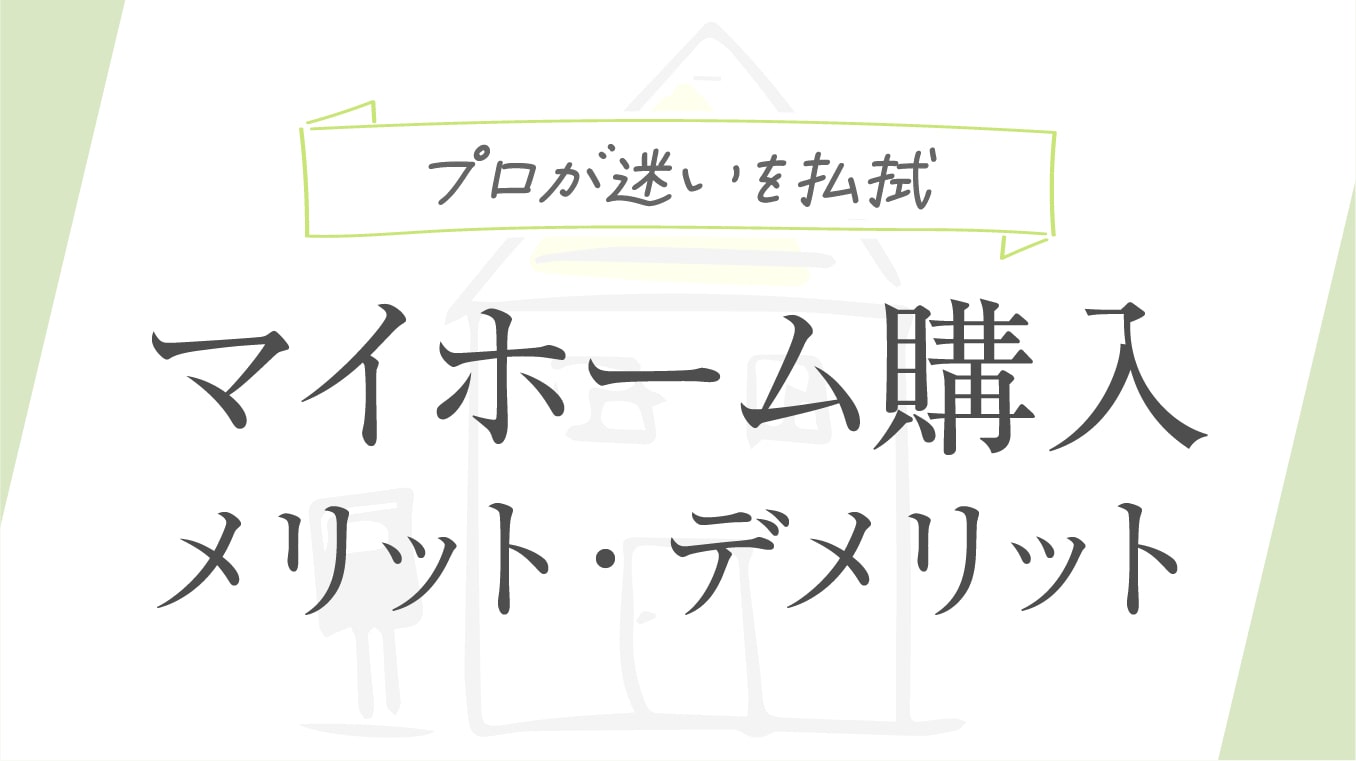
持ち家の固定資産税を節税する3つの方法


持ち家の固定資産税を節税する方法は以下の3つです。
- 分筆登記する
- 支払いにクレジットカードを使用する
- 非課税の土地があれば申告する
しっかりチェックしておきましょう。
1. 分筆登記する
分筆登記とは、1枚の登記簿から土地を分けることを指します。一筆から土地を分けるため、分筆と表記します。
分筆すると、利便性の低い土地の評価額を下げられますが、登記や測量に費用がかかってしまうことはデメリットです。



土地の評価額を下げられるのはメリットですが、分筆することで住宅を建てられなくなったり、リフォームできなくなったりする場合があります!
2. 支払いにクレジットカードを使用する
支払いにクレジットカードを使用すると、ポイントを貯められます。固定資産税の支払いは数万円にもなるため、クレジットカードのポイントを一気に貯められるでしょう。



利用できるならクレジットカードを使うのがいいですね!
ただし、クレジットカードを使用できる自治体は限定されているため、事前に確認しておくことが大切です。
3. 非課税の土地があれば申告する
私有地でも、公益性の高い土地は非課税となるため、確認して申告するのがおすすめです。道路や公園を保有している場合は、忘れず申告してください。



保有している土地があれば、申告すると節税できます!
所有している土地が道路に面していたり、公共の森林を保有していたりする場合は、非課税になる場合がほとんどです。
持ち家の固定資産税が増加する3つの原因


持ち家の固定資産税が増加するのは、以下の3つが原因です。
- 年末に住宅を取り壊す
- 空き家を放置している
- 家屋調査を拒否している
固定資産税を増加させないためにも、原因を押さえておきましょう。
1. 年末に住宅を取り壊す
固定資産税を減額させるためには、1月1日の時点で住宅が建っていなければなりません。そのため、年末に住宅を取り壊すと1月1日に建てるのは間に合わないでしょう。
年末に住宅を取り壊すと住宅用地とみなされなくなるため、固定資産税が増加してしまいます。



住宅を取り壊すと3倍以上の固定資産税がかかることもあるため、取り壊す予定がある方は注意してください!
2. 空き家を放置している
市町村から空き家に認定されると、住宅用地とみなされず固定資産税が上がってしまうため注意しましょう。
空き家対策特別措置法により、以下の条件を満たすと空き家に認定されてしまいます。
- 倒壊の危険がある
- 衛生的に問題がある
- 景観を損なっている
- 周辺の生活環境に問題がある



空き家認定されないように、しっかり管理しましょう!
別荘や実家を放置しておくと、管理がおろそかになり空き家の認定を受けてしまうかもしれません。
3. 家屋調査を拒否している



家屋調査を拒否すると正確に評価ができないため、固定資産税が高くなる恐れがあります!
家屋調査とは、固定資産税の算出をするために行われる調査のことで、実際に家に入って資産価値を評価します。



立ち入りを拒否したい場合は書類でも行えますが、実際の調査が行えず固定資産税が上がる場合も少なくありません!
固定資産税を節税したい場合は、調査に協力しましょう。
また、正当な理由なく拒否した場合は、罰則を受ける場合もあるため注意してください。
持ち家とマンションの固定資産税が異なる3つの理由


持ち家とマンションの固定資産税が異なる理由は以下の3つです。
- 建物の評価額
- 建物の耐用年数
- 軽減措置の種類の違い
持ち家とマンションで迷っている方は、違いを理解しておきましょう。
1. 建物の評価額
マンションは住んでいる部屋の広さが評価額のベースになりますが、持ち家は土地の評価額のほうが高くなります。
全体の土地を戸数で割った面積が所有分とみなされるため、マンションは建物の評価額のほうが高くなるのが特徴です。



将来売る予定があるなら持ち家がおすすめですね!
土地の評価額が高いと、不動産の価値が高くなるので売るときに有利になります。しかし、その分固定資産税も上がるので、慎重に比較しましょう。
2. 建物の耐用年数
木造の新築注文住宅の耐用年数は22年ですが、マンションは47年と長い傾向にあります。耐用年数を過ぎると、建物の価値が下がっていくので固定資産税も減額されることがほとんどです。



マンションより木造新築住宅のほうが建物の価値が下がりやすいので、固定資産税は安く済みます!
マンションか持ち家かを迷っている場合は、耐用年数をふまえて考えてみましょう。
3. 軽減措置の種類の違い
持ち家の軽減措置は改修工事をしたり、長期優良住宅に認定されたりすると適用されます。



マンションは新築住宅の場合、軽減措置が適用されますが、自分で改修したりリフォームしたりはできません!
軽減措置の種類が持ち家より少ないため、固定資産税が下がりにくいことがあります。



入居前から条件に合った物件を探す必要がありますね!
持ち家とマンションの違いについては、関連記事「【徹底比較】持ち家を買うならマンションと一戸建てどっち?価格・住みやすさ・選び方を解説」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
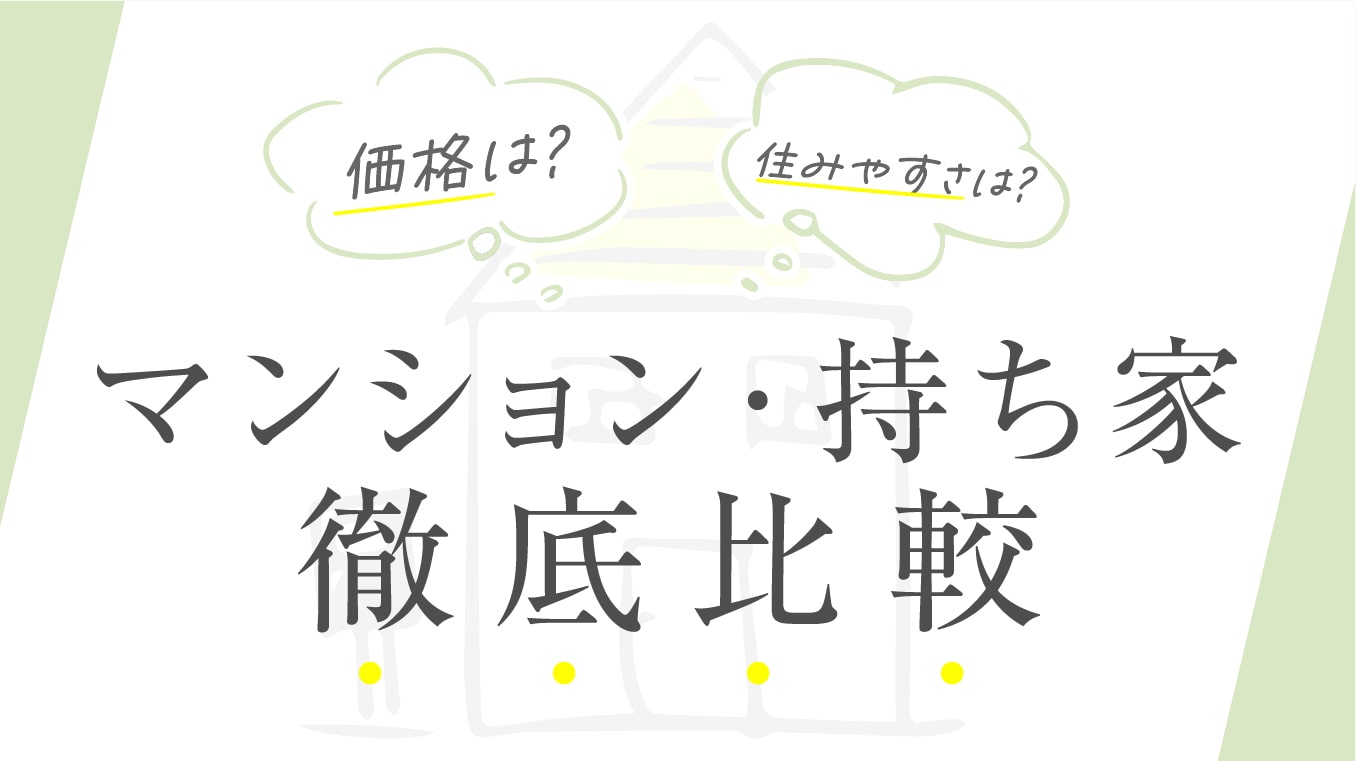
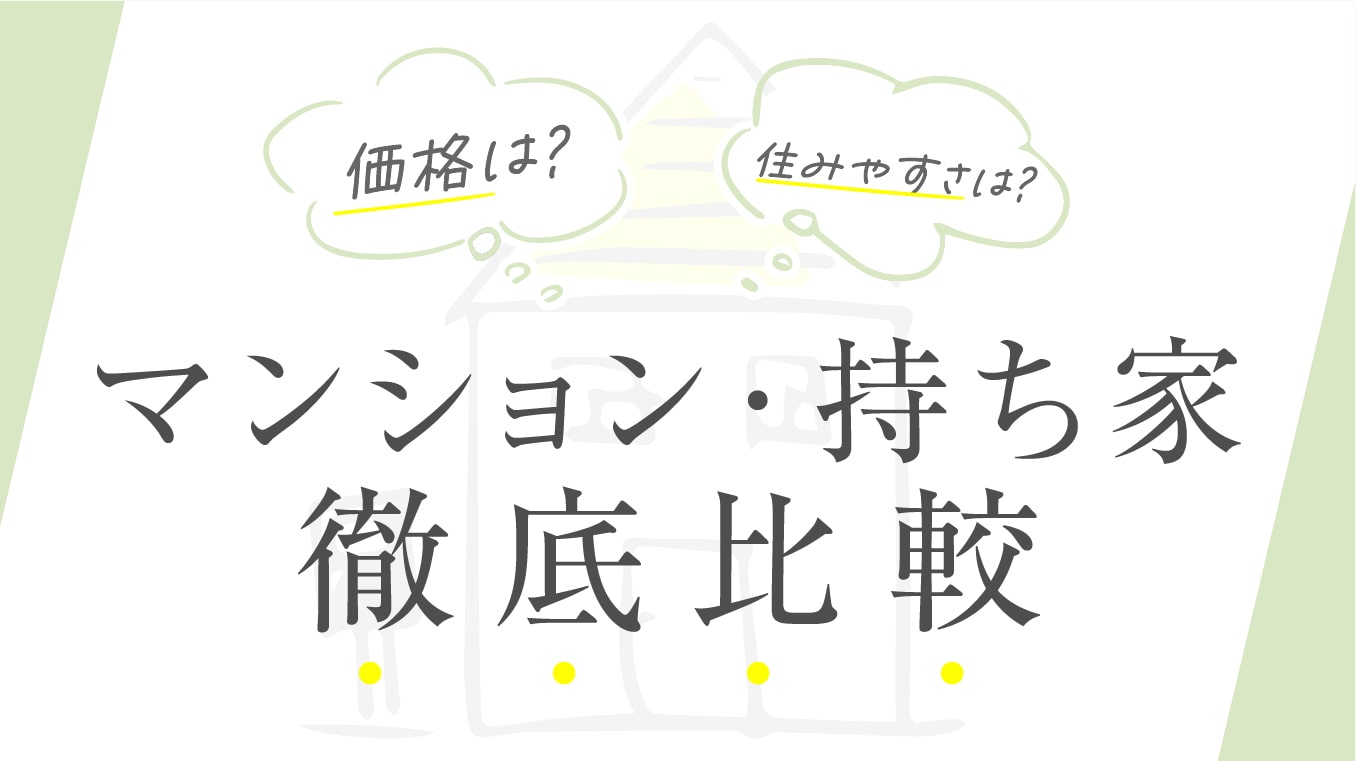
持ち家の固定資産税と土地計画税の支払時期と方法





固定資産税と都市計画税の税額が理解できたら、支払い時期や方法についてもチェックしておきましょう!
こちらでは、税金の支払いについて以下の2つを解説します。
- 支払時期
- 支払い方法
一つひとつ見ていきましょう。
1. 支払時期:4~5月に一括または年4回に分割
固定資産税の「納税通知書」は、4~5月頃に市区町村から届きます。その年の1月1日時点で固定資産を所有している方が対象です。そのため、1月2日に土地を取得したとすれば、その年の納税義務はありません。
納税通知書には、課税明細書が付いており土地、建物それぞれの固定資産税評価額が記載されています。
支払いは「一括払い」または「6月・9月・12月・2月の年4回分割」のいずれかの方法が選択可能です。



一括払いを選択したからと言って、税額が割り引かれることはありません!
2. 支払方法:クレジットカード・電子マネーも可
固定資産税は、以下の方法での支払いが可能です。
- 現金払い
- 口座振替
- クレジットカード
- 電子マネー
- スマホ決済



コンビニや金融機関に行かなくても、スマホを使って自宅からでも納税ができますね!
クレジットカードや電子マネーを使った納税では、ポイントが付与されるため、現金払いなどに比べてお得です。
持ち家の固定資産税はいくらかかるかを把握しておこう


持ち家の固定資産税を減らすためには、分筆登記したりクレジットカードで支払ったりすることが大切です。
また、固定資産税の軽減措置が適用される条件は、持ち家とマンションで異なります。それぞれの特徴を知ったうえで、マイホームの購入に踏み切りましょう。



持ち家とマンションはどちらもメリットがありますね!
持ち家の固定資産税は、年間10〜15万円が平均です。とはいえ、軽減措置を適用できれば負担を減らせる可能性があるので、ぜひ一度計算してみてください。



持ち家の固定資産税を減らすと、趣味や生活費に回せますね!
すーさんの相談窓口では、固定資産税の減らし方やマンションと持ち家のメリットなどを紹介しています。持ち家の購入に不安がある方や、できるだけ安く買う方法を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください!