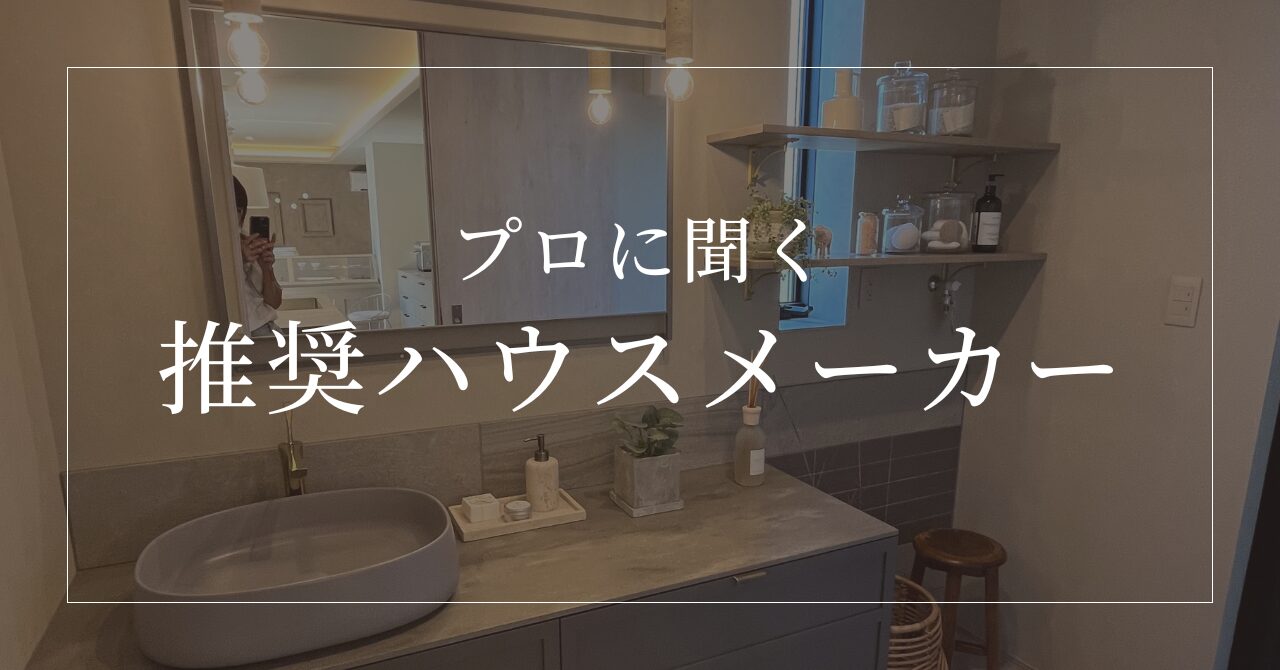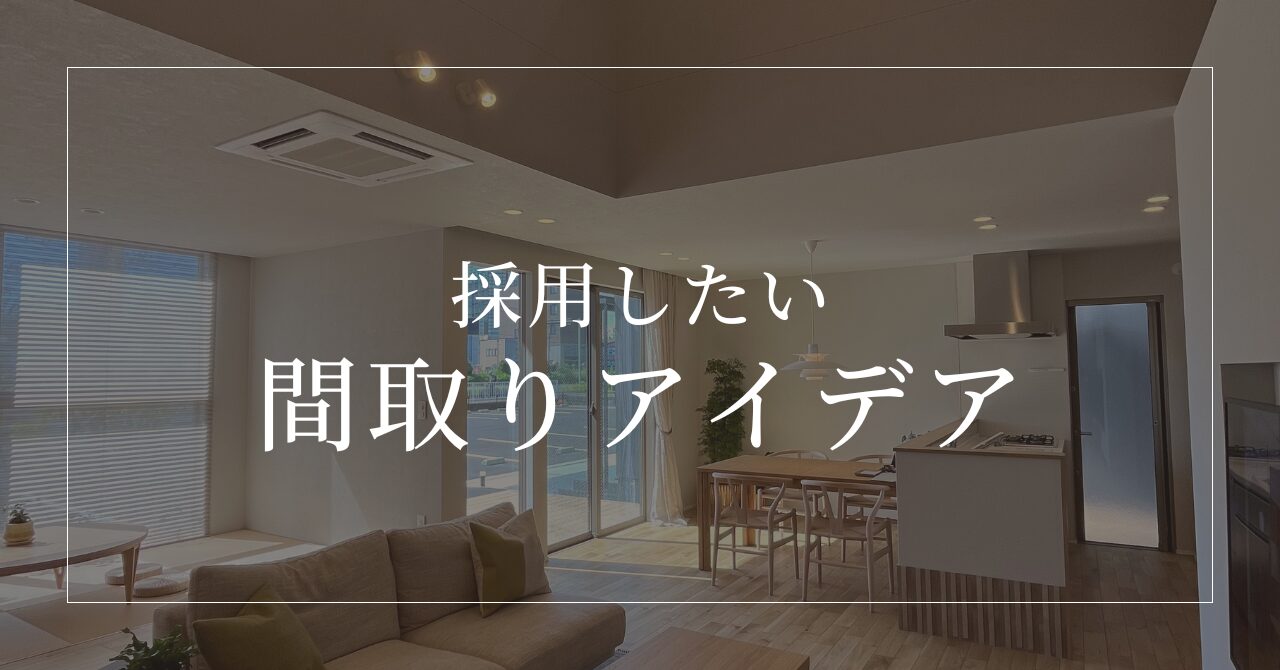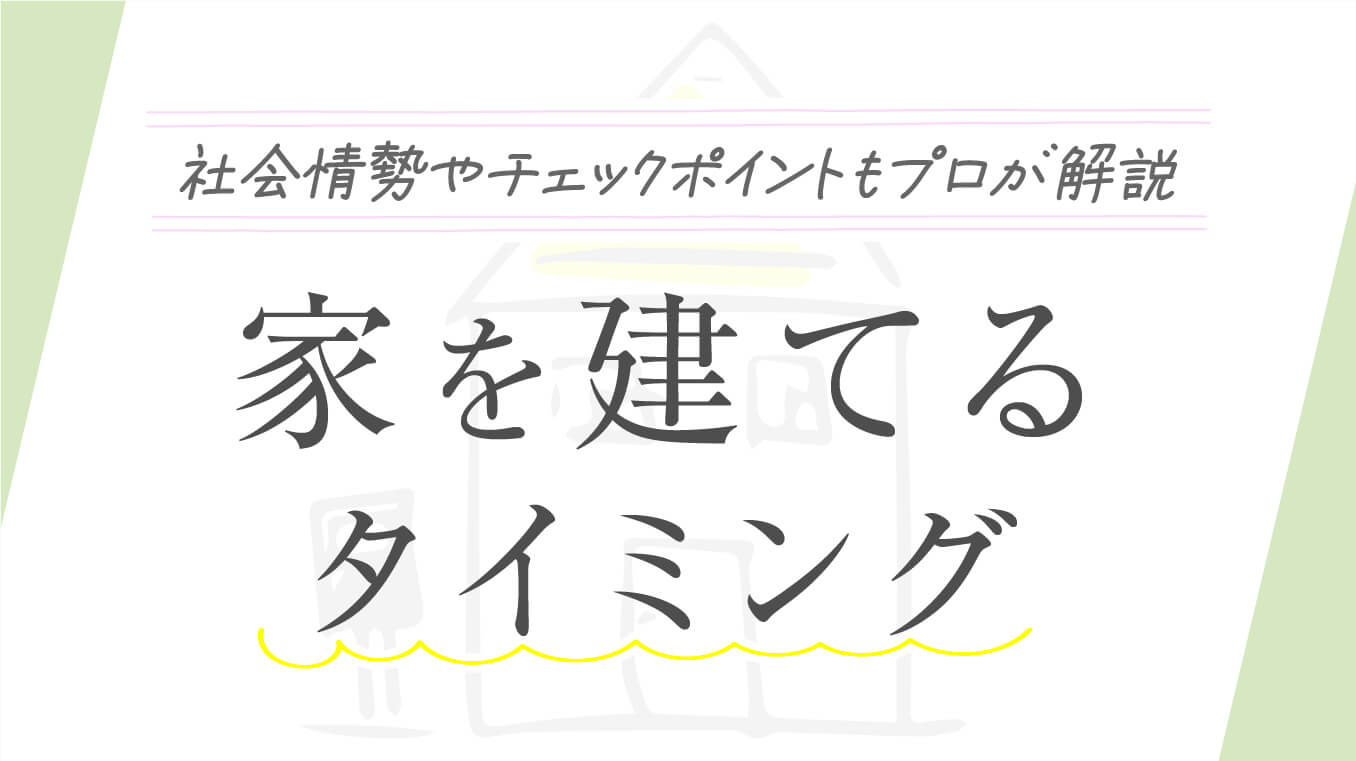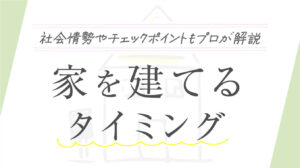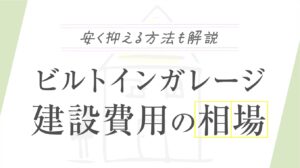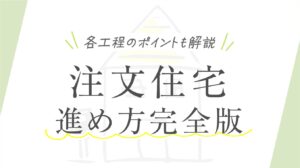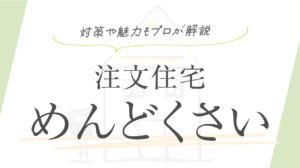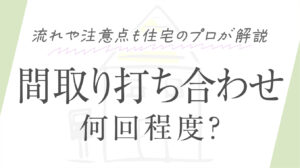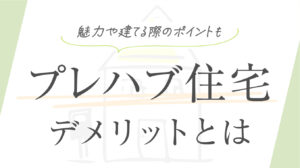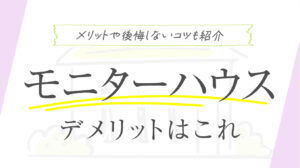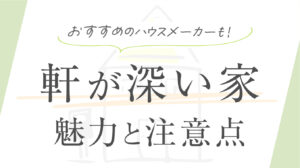「どのタイミングで家を建てるべきか悩んでいる」
「住宅価格が高騰していると聞くけど、今家を建てるべきではないのかな?」
「家を建てる際に活用できる補助金や優遇制度を知りたい」
住宅は多くの人にとって人生で最も高い買い物になる可能性があるため、どのようなタイミングで建てるべきか悩んでいる方は多いでしょう。
 あき
あき住宅ローンのことを考えると、早いほうがいいのかなとも思いますよね。
しかし、家を買うタイミングを誤ると、住宅ローンの返済が困難になる場合もあります。
この記事では、家を建てるタイミングについて以下の内容を解説します。
- ニーズ別のおすすめなタイミング
- 影響を与える社会情勢
- 活用できる優遇措置・補助制度
- 住宅ローン借入可能額の計算方法



大手ハウスメーカーに15年勤務した僕が監修しているので、信ぴょう性はバッチリです!
家を建てるタイミングを考える際のポイントが理解できる内容になっているので、ぜひ参考にしてみてください。
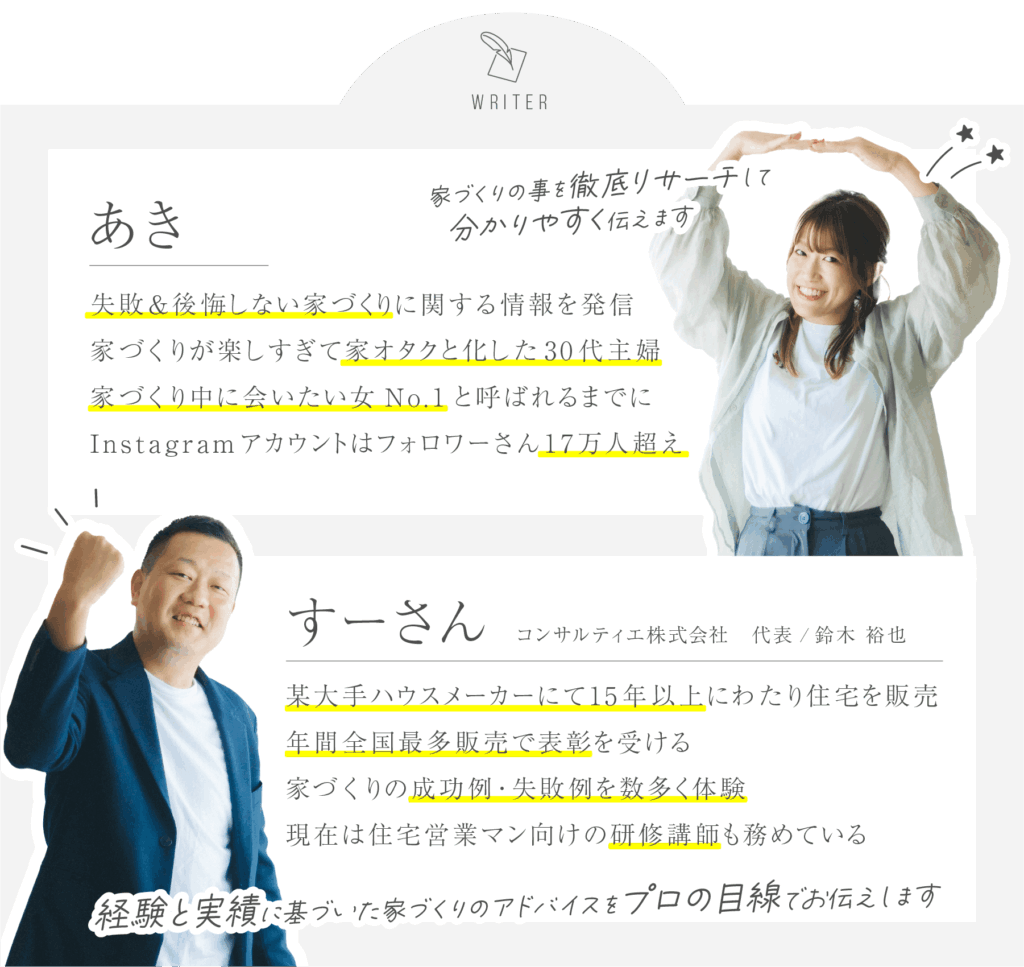
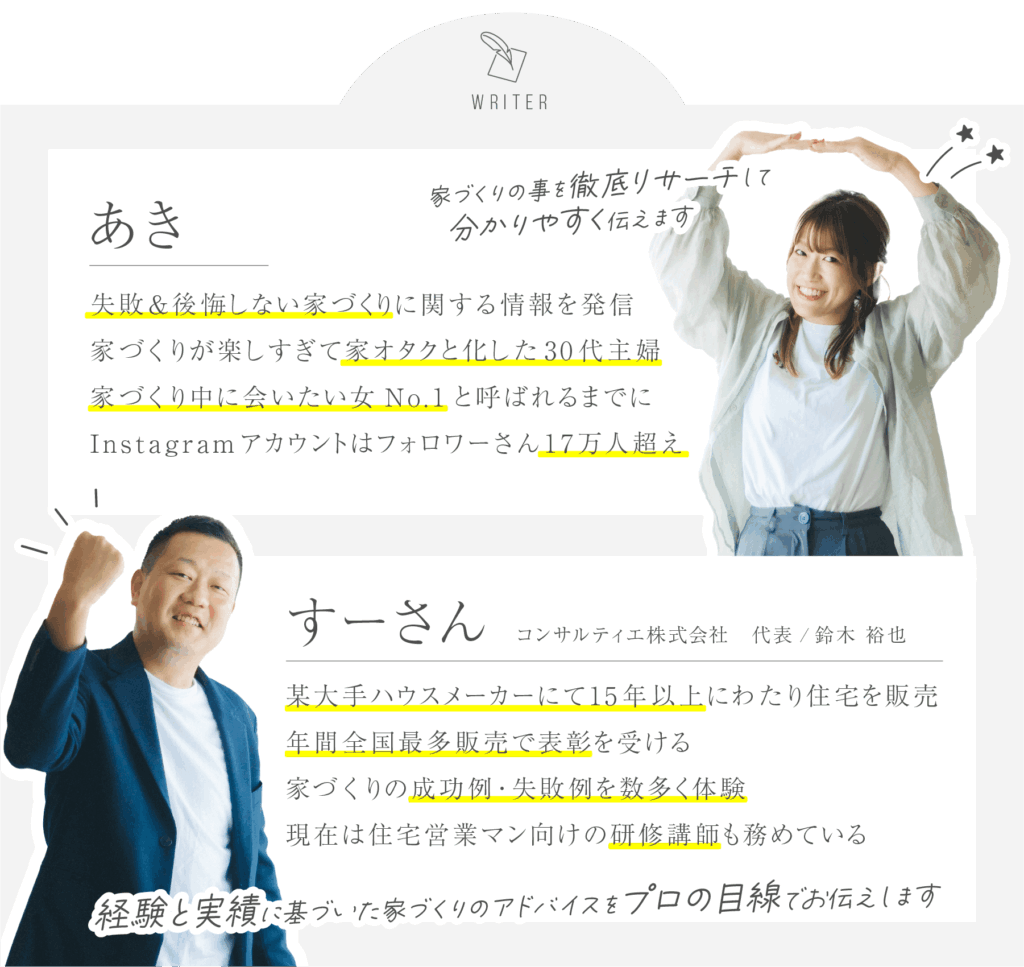
家を建てるときに知っておきたい3つの平均


家を建てることを検討する前に、以下の3つの平均をチェックしておきましょう。
- 平均年齢
- 平均世帯年収
- 平均居住人数
それぞれチェックしておけば、目安にできます。
1. 平均年齢
国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によると、新築注文住宅を建てる平均的な年齢は43.8歳でした。分譲戸建て住宅を購入する平均年齢は38.4歳で、新築注文住宅より若い年齢で購入していることがわかります。



新築注文住宅は分譲戸建て住宅よりも費用が高くなる傾向にあるため、購入する年齢が遅くなりやすいのです!
ただし、新築注文住宅では購入費用が高くなることから、ローンの返済期間が長くなります。定年退職後の負担を減らしたい方は、人生設計をしっかり立てていつ購入するかを決めましょう。
2. 平均世帯年収
国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によると、平均世帯年収は注文住宅は全国で平均801万円、三大都市圏では平均896万円でした。
また、国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、平均年収は458万円なので、注文住宅を購入する人は約2倍の年収があることがわかります。注文住宅は費用が高いことから、給与に余裕を持ててから購入する人が多い傾向にあります。



平均より給与が高い人が注文住宅を購入しやすいんですね!
3. 平均居住人数
国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によると平均居住人数は3.2人で、3人が29.3%と最も多いことがわかります。子ども1人と両親の3人家族が注文住宅を建てる傾向にあるのが特徴です。
居住人数が増えるとスペースが必要なため、広い敷地面積の確保が欠かせません。すると、土地代が高額になります。



新しく家を建てる予定の方は、それぞれの平均をチェックしておきましょう!
【世帯状況別】家を建てるタイミング2選


世帯状況で見ると、家を建てる最適な時期は以下の2つのタイミングです。
- ローンの完済が定年退職を超えない年齢
- 支払総額の2割分の資金が溜まったとき
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. ローンの完済が定年退職を超えない年齢
住宅ローンを組む場合、完済時に定年退職の年を超えない年齢で家を建てることが大切です。定年退職後には、まとまった収入がないことから年金や貯蓄から返済する必要があるため、老後の生活に悪影響を与えてしまいます。
なお「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によると、住宅ローンの返済期間は30年以上です。



60歳で定年退職する場合は30歳、65歳では35歳までに家を建てると、給与所得がある内に返済を終えられる計算ですね!
「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によると、注文住宅を取得した世帯主の年齢で最も多い年代は30歳代で36.9%です。多くの方は30歳代の内に家を建てて、住宅ローンの支払いを始めているのが現状です。
2. 支払総額の2割分の資金が溜まったとき
住宅購入資金として、支払総額の2割の貯蓄ができたときが家を建てるタイミングの目安となります。住宅ローンを組む際に必要な頭金が、支払総額の2割程度と言われているためです。
たとえば、支払総額3,000万円に必要な頭金は600万円程度です。



借入額を減らせるので返済期間が短くなり、金利の支払総額も抑えられますよ!
家を建てるタイミングは、支払総額の2割程度が貯まったときが適期と言えるでしょう。
【ライフイベント別】家を建てるタイミング5選
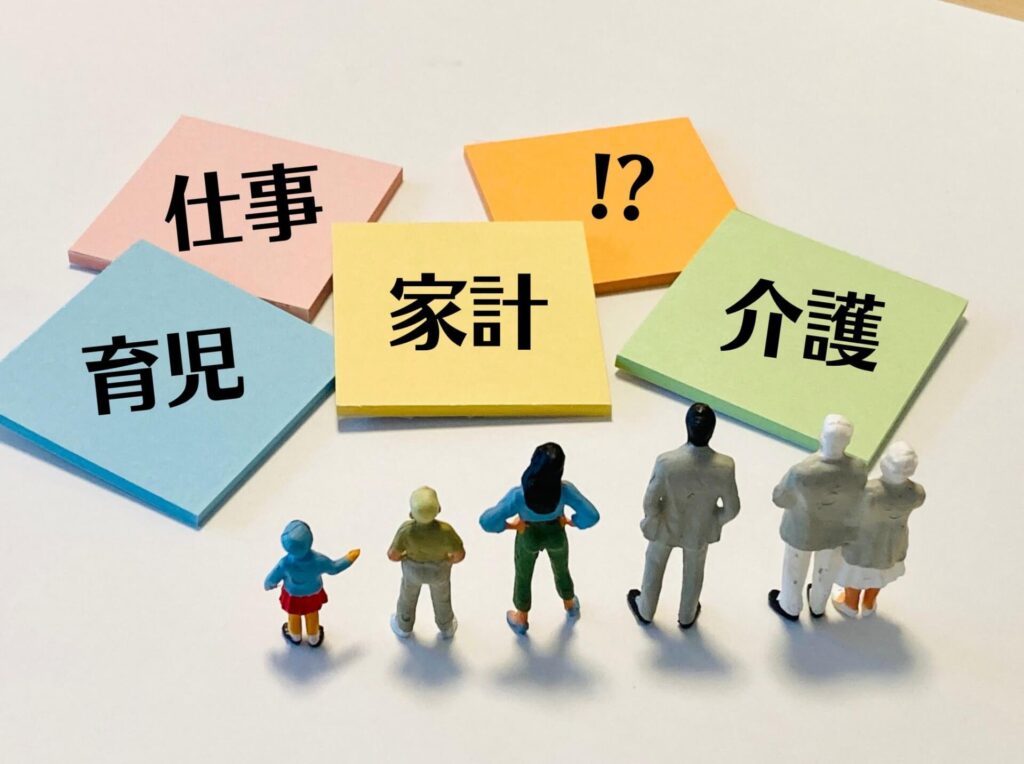
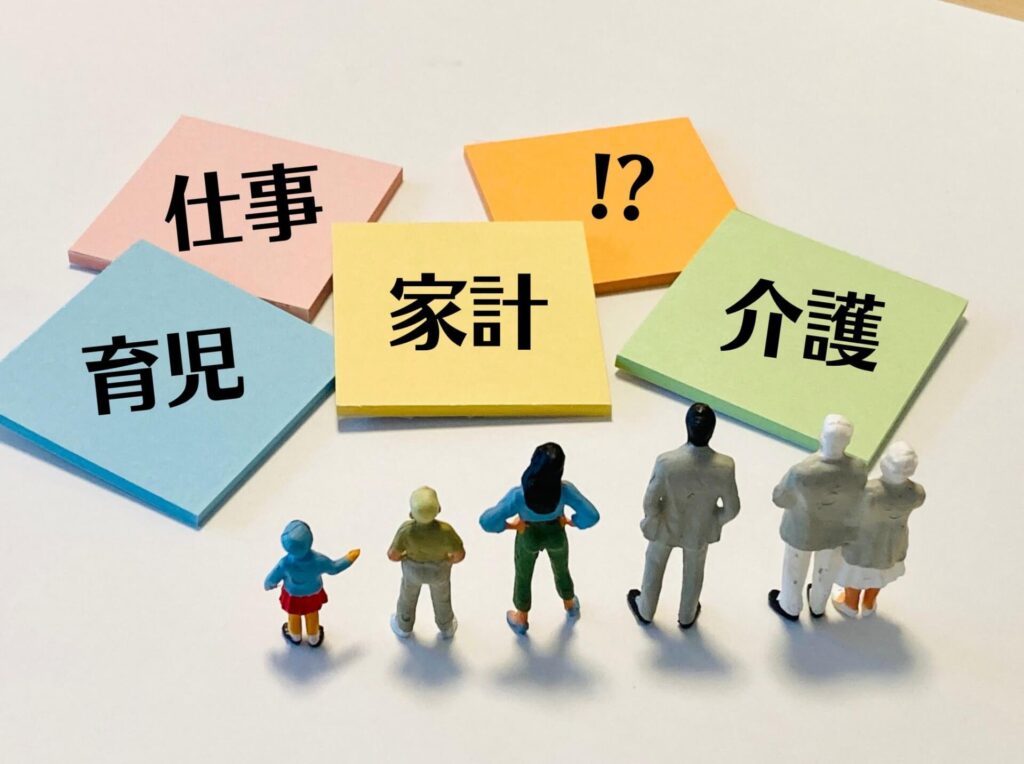
家を建てるタイミングは、自身のライフイベントが大きな影響を与えます。住宅購入に影響を与えるライフイベントは、主に以下の5つです。
- 結婚
- 出産
- 子どもの入園・入学
- 親の介護
- 子どもの独立
一つひとつ見ていきましょう。
1. 結婚
結婚は住宅購入をはじめ、その後の人生設計を考える良い機会です。比較的若い時期に住宅ローンの返済を始められるため、定年までに完済できる可能性が高くなります。



ただし、家を建てた後に「転職する」「子どもが生まれる」など、将来的な生活の変化を見通しにくいタイミングとも言えます!
2. 出産



出産前後の時期は、育児や子どもの就学環境まで検討するが必要あるタイミングです!
子どもが生まれると夫婦だけの生活に比べて物が多くなり、広いスペースが必要です。
子どものいる生活を具体的にイメージできるため、間取り等を考えやすいタイミングでもあります。



ただし、出産前後は生活が慌ただしいため、じっくり検討する時間を取りにくい点がデメリットです!
3. 子どもの入園・入学
保育園の入園や小学校の入学時期は、子どもの友達関係や就学環境を変えないために家を建てるケースが多いです。
入園や入学した後に家を建てると、転校による環境の変化から子どもが多くのストレスを感じてしまいます。



たしかに、子どもが小学生になってからだと家を建てにくいかも…
子どもの成長を考えると、入園・入学時期は家を建てるタイミングとして適しているでしょう。
4. 親の介護
両親と同居している方は、介護が必要になったタイミングで家を建てるケースがあります。



介護がスムーズにできるよう、家の中をバリアフリーにするといったリフォームが必要です!
介護リフォームには多額の費用がかかるため、家自体を新しく建てて住み替える選択をする人は少なくありません。
将来の介護を想定して、バリアフリー住宅を建てることを検討してみても良いでしょう。
5. 子どもの独立



子どもが家を出たタイミングに、夫婦の老後を考えて家を建てることがあります!
子どもが独立した後には、多くの部屋が不要になります。家が老朽化している場合や賃貸に住んでいる方は、夫婦だけの暮らしを想定して小規模な家を建てる選択を検討してみても良いでしょう。
子どもの独立といったライフイベントにあわせて家づくりを考える際には、LIFULL HOME’Sの「はじめての家づくりノート」を参考にしてみてください。



間取り案といった情報が充実しているため、これからの生活にあわせた家づくりを考える際の参考になります!
LIFULL HOME’Sの家づくりノートの詳細は、関連記事「【めっちゃ簡単】家づくりに役立つノートをもらう方法!よくある疑問もスッキリ解決(PR)」で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください!


【季節別】家を建てるのは避けたいタイミング2選


家を建てるのがおすすめのタイミングがあるように、避けたいタイミングもあります。以下の2つはなるべく避けるようにしましょう。
- 冬場は工期が長引きやすい
- 夏場は梅雨や台風による影響で着工が延期になるケースがある
スケジュール通りに家を建てたい場合は、それぞれチェックしておいてください。
1. 冬場は工期が長引きやすい
大雪の日は物流がストップする可能性が高いため、施工がスケジュール通りに進みません。また、冬は日照時間が短いため、夏に比べて施工に時間がかかりやすいのが特徴です。
スケジュール通りに家を建てたいなら、工事の時期を冬以外にするのがおすすめです。春先か9~10月に着工のスケジュールを立てるとスムーズに進みやすいでしょう。



冬はさまざまな原因で工期が長引くことを覚えておきましょう!
2. 夏場は梅雨や台風による影響で着工が延期になるケースがある
雨の場合は着工が延期になり、スケジュールが後ろ倒しになることもあるため、梅雨の時期はできるだけ避けましょう。足場を作るときに雨が降っていると危険なので、延期になりやすい傾向にあります。
延期になると、なかなか完成が見えず時間がかかりますね…
そのため、台風の時期はなかなか着工できず、スケジュール通りに進まないかもしれません。家の工事をスムーズに進めるには、夏を避けて春に着工できるように計画しましょう。
家を建てるタイミングに影響を与える5つの社会情勢


家を建てることを検討する際に「今買うと高いのではないか」と心配している方も多いのではないでしょうか。



今後社会情勢により住宅価格がどのように変動するかわからないため、今は買うタイミングではないとは言えません!
こちらでは、家を建てるタイミングに影響を与える5つの社会情勢について解説します。
- 円安
- ロシアのウクライナ侵攻
- 木材価格の高騰
- 金利の上昇
- 空き家の増加
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 円安
家の建材の多くは輸入品であるため、円安になると価格が高騰します。円安傾向は2022年に入ってから加速し、一時は1ドル=160円台(2024年時点)にまでなりました。
円安傾向は約38年ぶりの高水準です。円安がいつまで続くのかは誰にもわかりませんが、為替レートは注意して見ておく必要があるでしょう。
2. ロシアのウクライナ侵攻
2022年に始まったロシアのウクライナ侵攻は、住宅の価格高騰の大きな原因です。日本政府とロシア政府それぞれが木材製品の輸出入を禁止しているため、木材価格が高騰しています。



ロシア産の赤松が輸入できないため、合板(ベニヤ)は生産量が減り価格が2倍にまで上昇しています!
ロシアのウクライナ侵攻は終結の目処が見えないため、今後も木材価格が元に戻る見通しは立ちません。
3. 木材価格の高騰
木材価格の高騰は、ロシアのウクライナ侵攻だけが原因ではありません。木材価格は2021年頃から上昇傾向にあり、ウッドショックと呼ばれています。



ウッドショックの原因は、アメリカや中国の住宅需要の増加や労働力不足です!
農林水産省が発表している「木材流通統計調査」によれば、多少の下落傾向はあるものの高止まりが続いています。
ウッドショックでも家の購入がおすすめの理由については、関連記事「【迷わない】今家を買うべきか?ウッドショックでも購入がおすすめな理由と注意点を解説」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
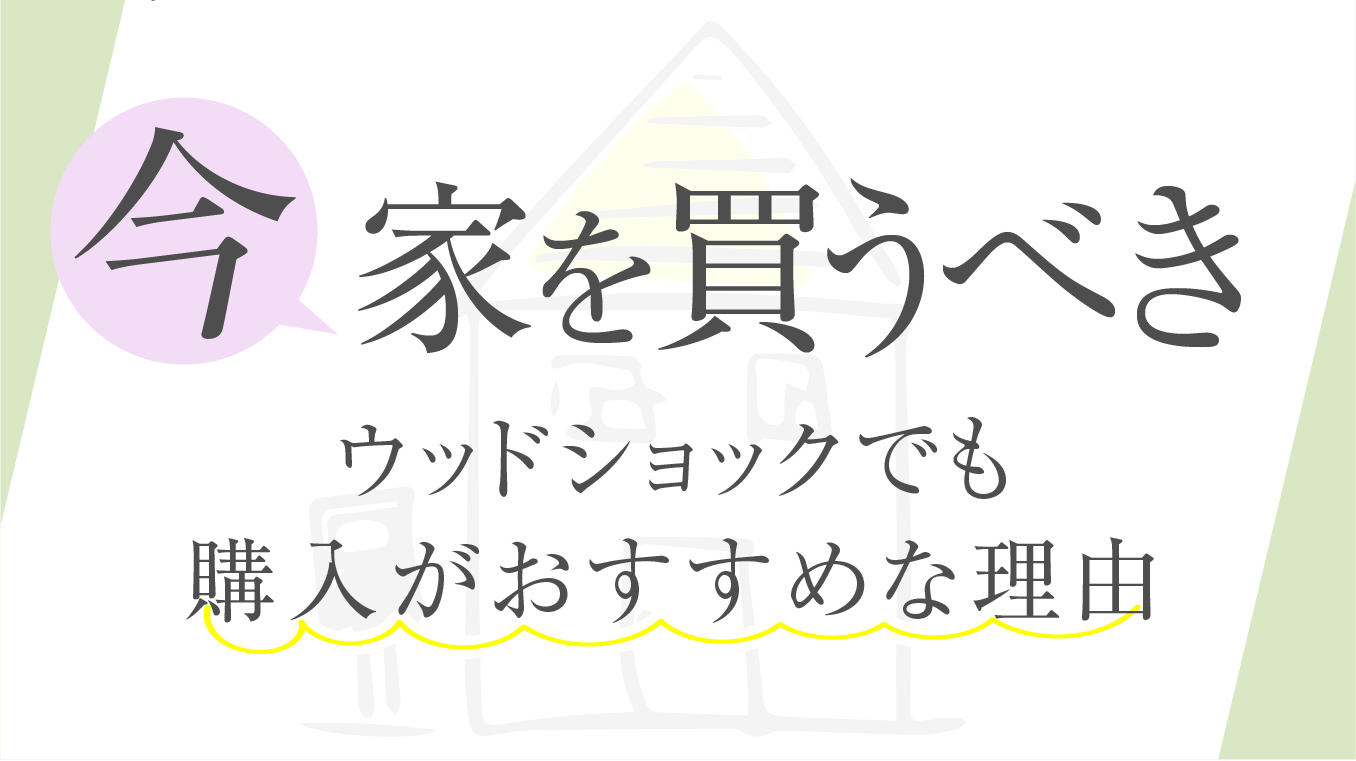
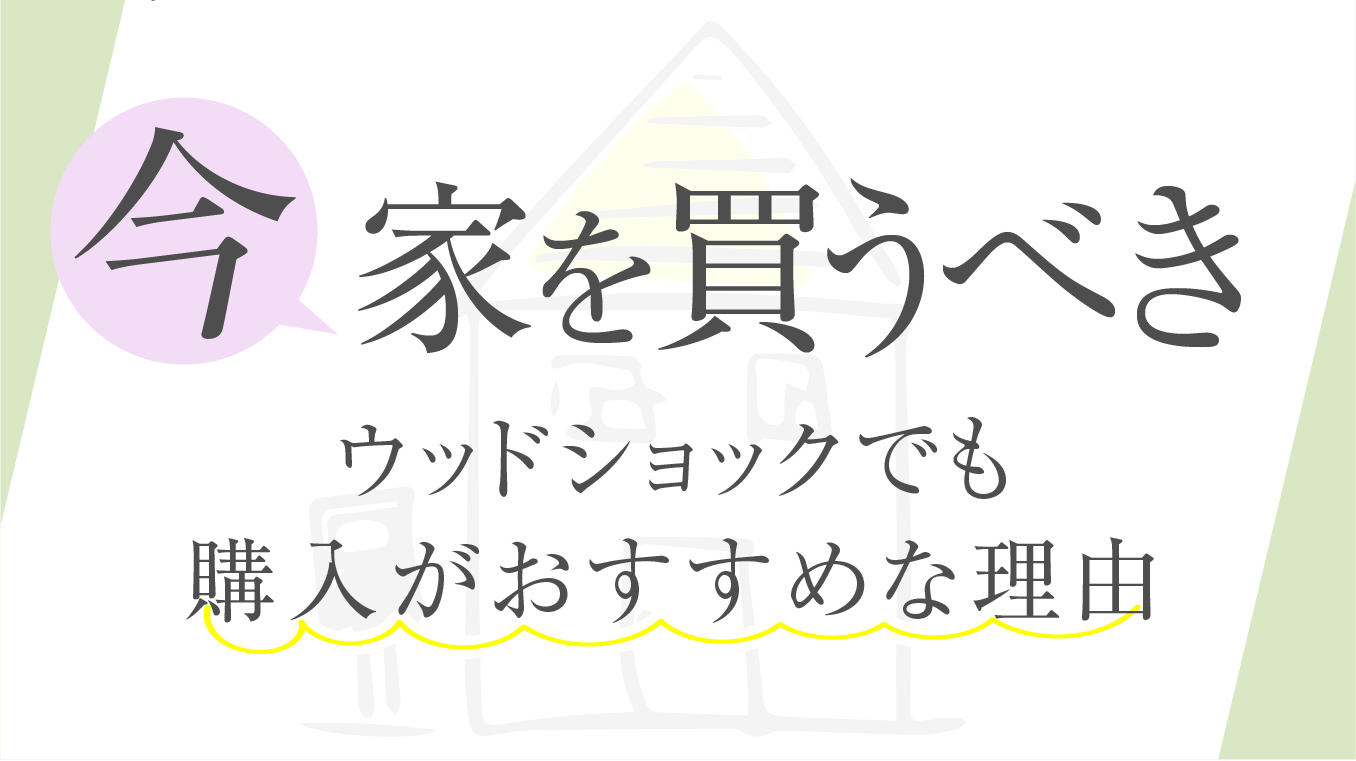
4. 金利の上昇
住宅ローンの金利は、変動金利は低水準で安定しているものの、固定金利は引き上げ傾向です。住宅ローンを固定金利で借りれば、完済まで同じ金利が適用されます。



固定金利の場合、低金利のときに住宅ローンを組めば総支払額を抑えられます!
しかし、固定金利が上昇傾向にある現在は、金利面での恩恵を受けることが難しい状況です。
5. 空き家の増加



空き家の増加によって不動産市場の需給バランスが崩れ、今後買い手市場になる可能性があります!
高齢者の増加に伴って空き家が増え、住宅の売却や譲渡が増加するためです。空き家は、約800万人の団塊世代全員が後期高齢者になる2025年以降はさらに増加すると推定されています。
そのため、空き家の増加にともない中古住宅を安く取得できるようになる可能性がありますよ。
家を建てるタイミングで活用できる優遇措置・補助制度


家を建てる際には、国や自治体の優遇措置や補助制度を活用できます。家の性能や借入内容によっても変わるため、住宅の設計やローンの契約前に確認しておきましょう。
- 補助制度
- 減税制度
- 優遇制度
それぞれ詳しく解説します。
1. 補助制度
国による補助制度は、高性能住宅の建設や環境に配慮をした建設方法を取った場合に受け取れます。



国は省エネや環境に良い住宅づくりを奨励しているから、様々な補助金制度を用意しているんですね!
省エネ・創エネによってエネルギーコストを減らす住宅「ZEH(ゼッチ)」や、建設時や運用時のCO2排出量を減らす「LCCM住宅」などが対象です。
各補助制度と金額は、以下の表を確認してみてください。
| 補助金名 | 対象 | 補助金額 |
|---|---|---|
| こどもエコすまい支援事業 | 「高い省エネ性能を持つ住宅」を建てる方で、18歳未満の子どもがいる、または夫婦どちらか39歳以下 | 100万円/戸 |
| ZEH(ゼッチ)支援事業 | ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を建てる方 | 55~100万円 |
| LCCM住宅整備推進事業 | LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅を建てる方 | 140万円/戸 |
| 地域型住宅グリーン化事業 | 認定長期優良住宅を建てる方 | 90万円~ |
ハウスメーカーは、様々な高性能住宅の販売に力を入れています。



カタログや住宅展示場などで、情報収集をしておくと良いでしょう!
2. 減税制度
家を建てる際には、様々な減税制度を利用できます。住宅ローンを利用した場合に所得税控除を利用できるだけでなく、不動産所得税や贈与税の軽減措置もあります。



主な減税制度は、以下の表を確認してみてください!
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 住宅借入金等特別控除 | 年末時に残っている住宅ローンの額の0.7%分が、その年に支払った所得税から控除 |
| 不動産取得税の軽減 | 2027年3月31日までに取得した場合の税率は3%(本来4%) |
| 固定資産税の軽減 | 通常の住宅だと3年間、認定長期優良住宅だと5年間、固定資産税額が2分の1 |
| 贈与税 住宅取得等資金の非課税措置 | 家を新築・購入する際に父母や祖父母から購入資金の贈与を受けた場合に、一定金額まで贈与税が非課税になる |
機能性の高い認定長期優良住宅を建てた場合には固定資産税額が軽減される制度もあるので、住宅購入の際には参考にしてみてください。
3. 優遇制度
優遇制度とは、金利や保険料の軽減措置です。主な優遇制度は、以下の3つです。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 住宅ローン【フラット35】の金利優遇 | 借入金利を一定期間引き下げる(フラット35維持保全型の場合5年間分トータル0.5%引き下げなど) |
| 火災保険の優遇制度 | 耐火性能の高い住宅は火災保険料が軽減される |
| 地震保険優遇制度 | 耐震等級により地震保険が優遇される(耐震等級1であれば10%、耐震等級2であれば30%、耐震等級3であれば50%の割引) |



補助制度や減税制度と同様に、高性能住宅は優遇制度を活用しやすくなっています!
タイミング以外も重要!家を建てるときにチェックすべき3つのポイント


家を建てるときは、タイミング以外にも以下の3つのポイントをチェックしておきましょう。
- 希望を実現できるハウスメーカーを選ぶ
- 土地は慎重に探す
- 十分な耐久性である
後悔しないためにも確認しておいてください。
1. 希望を実現できるハウスメーカーを選ぶ



家を建てるときは、自分の希望を実現できるハウスメーカーなのか見極めましょう!
特に外観や間取りにこだわりがある場合は、過去のデータや施工事例をチェックしておくと、理想を実現できるか確認できます。
まずはどのような家を建てたいのかを洗い出し、希望が実現できそうなハウスメーカーを数社に絞っておくとスムーズに家づくりが進められるでしょう。
2. 土地は慎重に探す
土地には以下のような制限があるケースがあるため、慎重に探さなければなりません。
- 用途制限
- 建蔽率・容積率
- 日影制限
- 宅地造成規制
このような制限があると希望の土地に住宅を建てられないことがあるので、ハウスメーカーと相談しておきましょう。また、日当たりや周囲の環境も事前にチェックしておくと後悔を防げるので、家づくりの前にはチェック必須です。



土地の制限をチェックしておけば、家探しが振り出しに戻ることはありませんね!
土地探しのコツについては、関連記事「【まるわかり】土地探しのコツ7選!家づくりのプロが失敗例や基礎知識もあわせて紹介」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
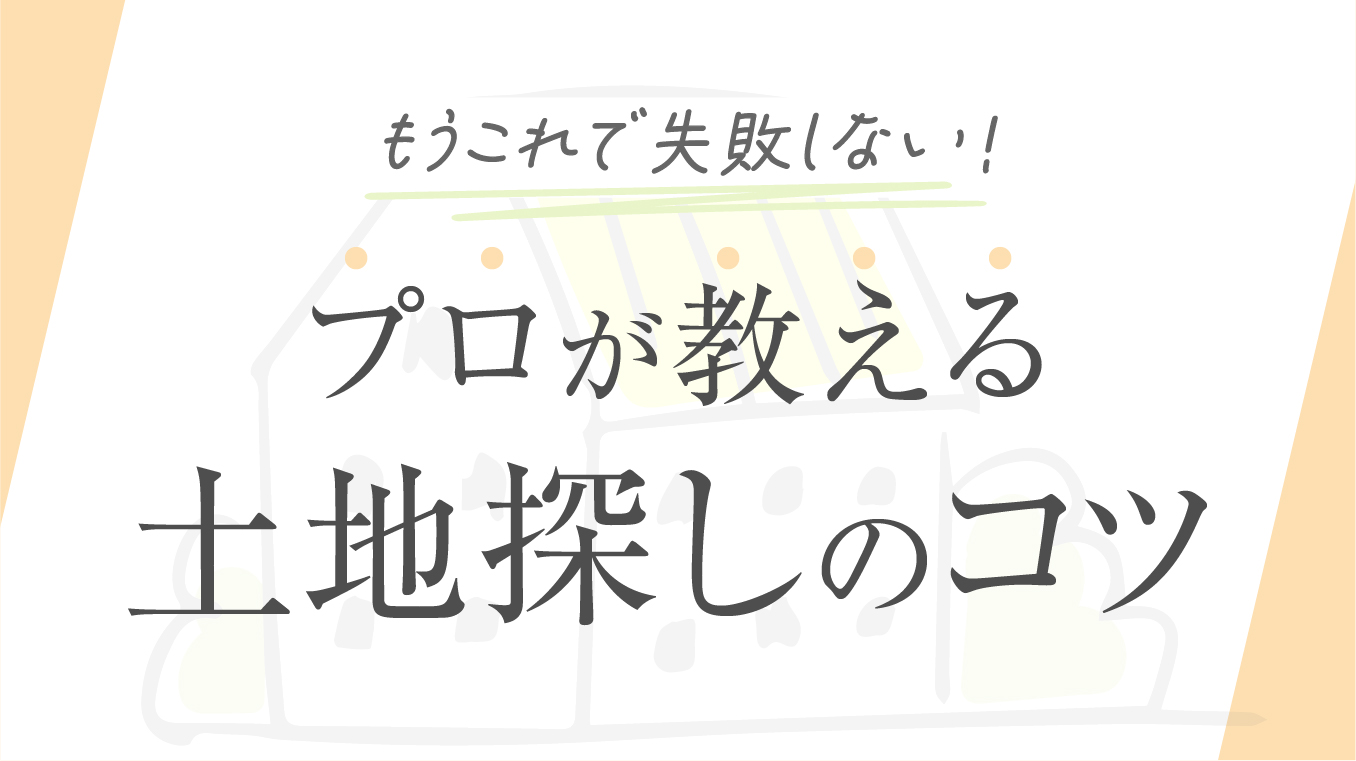
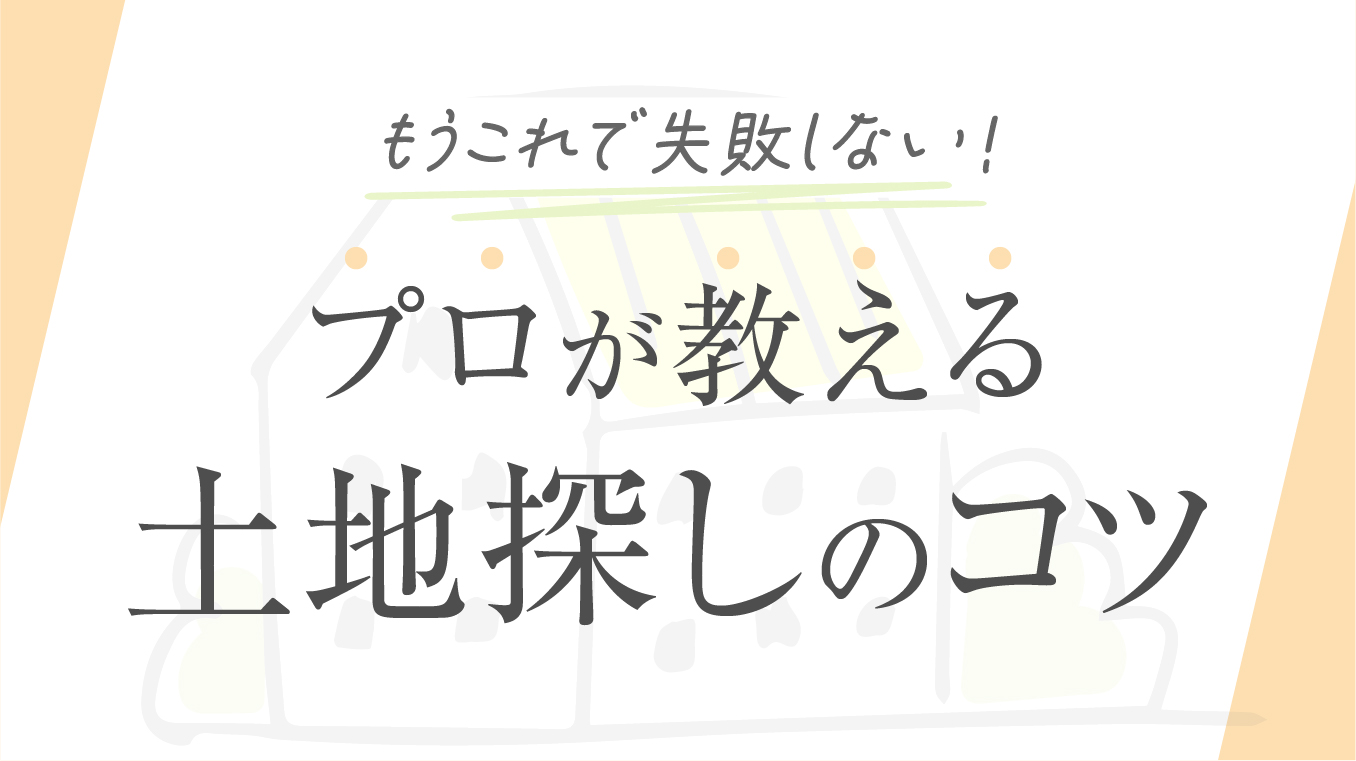
3. 十分な耐久性である
耐震性や耐久性をチェックして、安心して暮らせるマイホームを建てましょう。耐震性や耐久性はハウスメーカーによって性能が異なるので、しっかり比較することで安心して長く暮らせる住宅を建てられます。
そのため、ハウスメーカーを選ぶ際にはホームページをチェックしておいてください。日本では近年災害が増えているため、耐久性がある住宅を選ぶことで後悔を減らせるはずです。



耐震性能2~3の住宅なら安心して暮らせるでしょう!
家を建てるタイミングでチェック!住宅ローン借入可能額の計算方法


家を建てる際には、自身がいくら住宅ローンを借りられるのか気になる方は多いでしょう。借入可能額を計算する際には、まず年間返済額の上限を以下の式で計算します。
年間返済額 = 返済負担率 × 税込年収
返済負担率とは、年収に占める返済額の割合のことです。多くの金融機関では、30〜35%程度に設定されています。年間返済額が計算できたら、以下の式で借入可能額を計算します。
借入可能額 = 年間返済額の上限 ÷ 12÷ 4428 × 100万円
「4428」とは、審査金利4%で100万円を35年間借入た場合の月々の返済額のことです。審査金利とは住宅ローンの審査のためだけに用いる金利で、多くの場合4%程度に設定されています。



計算がちょっと難しいという方は、年収別の借入可能額の一覧を以下の表で確認してみてください!
以下の表は、返済負担率30%・審査金利4%で計算した場合の年収別の借入可能額です。
| 年収 | 借入可能額 |
|---|---|
| 300万円 | 1,690万円 |
| 400万円 | 2,250万円 |
| 500万円 | 2,820万円 |
| 600万円 | 3,380万円 |
返済負担率や審査金利は金融機関によって異なるため、詳しい借入可能額は金融機関に確認が必要です。



住宅ローンの借入可能額を調べるには、モゲチェックの活用がおすすめですよ!
購入する家が決まっていなくても仮審査ができるので、自身がいくらまで住宅ローンを組めるのか調べてみると良いでしょう。また、主要銀行の金利を一括で比較できるため、ご自身に最適な金融機関を探せます。
モゲチェックの詳細は、関連記事「【金利0.1%の差が命取り】住宅ローンの負担を下げるにはモゲチェックがおすすめ!使い方をわかりやすく解説」で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください!


家を建てるタイミングを見極めて理想のマイホームを手に入れよう


家を建てるタイミングは、資金面やライフイベントなどを考慮して検討してみると良いでしょう。
また、家を建てる際には、補助金や優遇制度を活用できます。国や自治体からサポートしてもらえる対象となるか確認しておくと、資金面の負担を軽減できるので安心してマイホームを実現させられるでしょう。
なお、マイホームを建てるタイミングや資金の工面についてお悩みのある方は、専門家に相談することをおすすめします。「すーさんの相談窓口」なら住宅会社選びやローンの組み方など、家づくりのことならどのようなことでも無料で相談できます。



何から考えれば良いかわからないという方は、まず私までお気軽に連絡してみてください!