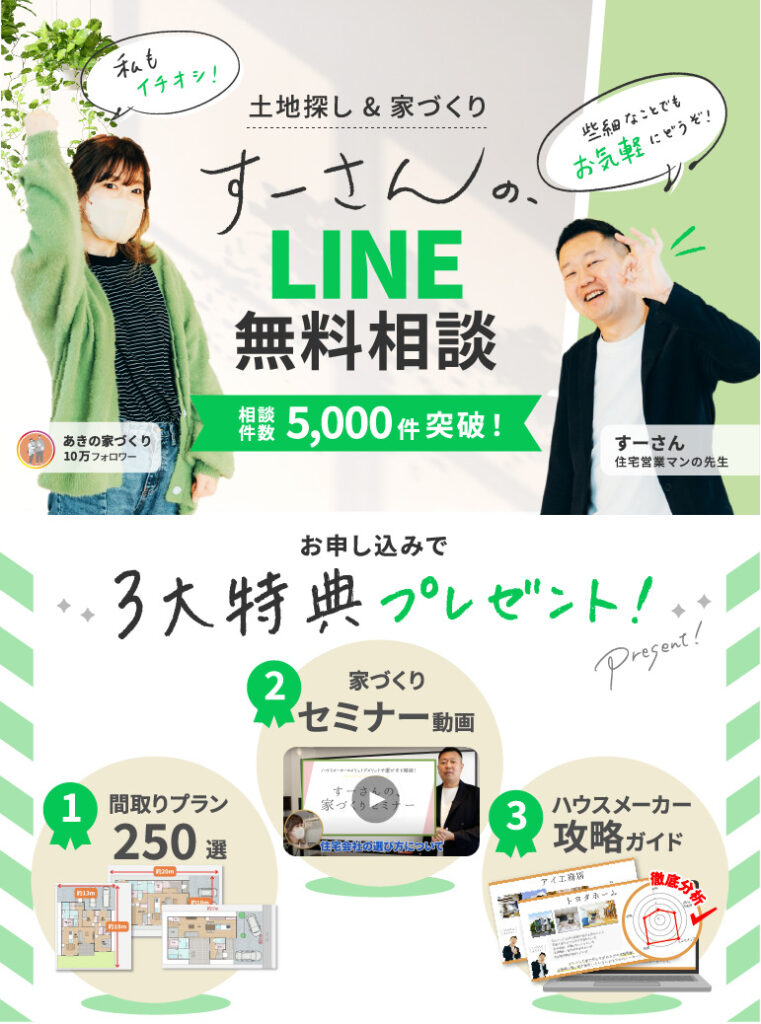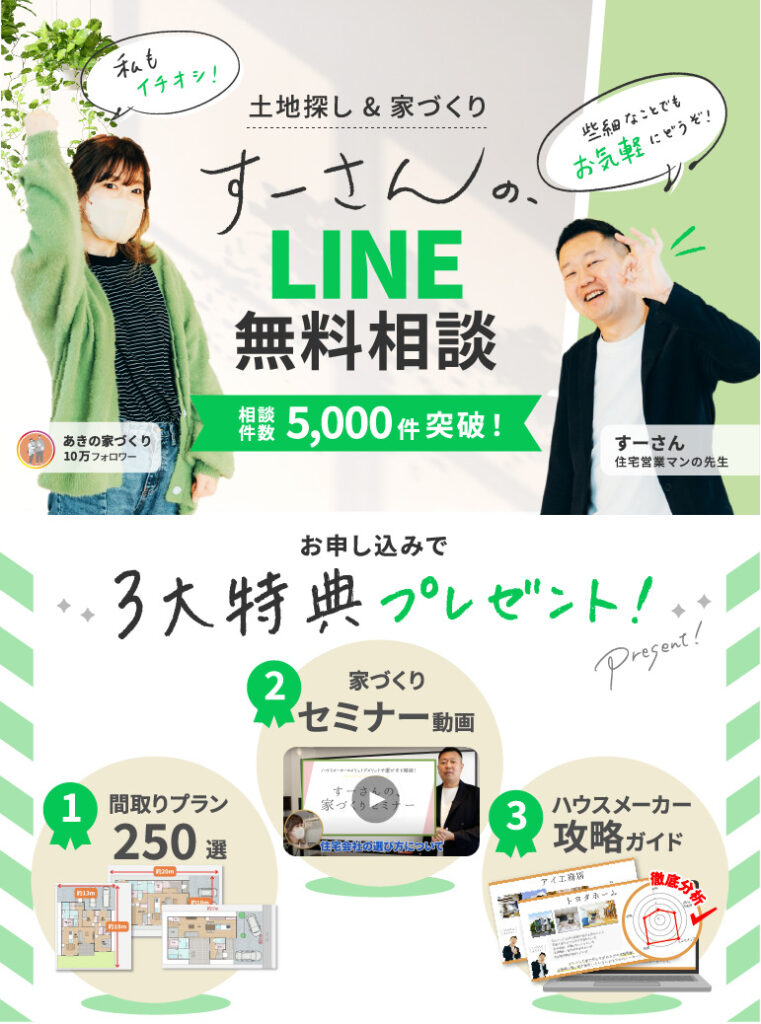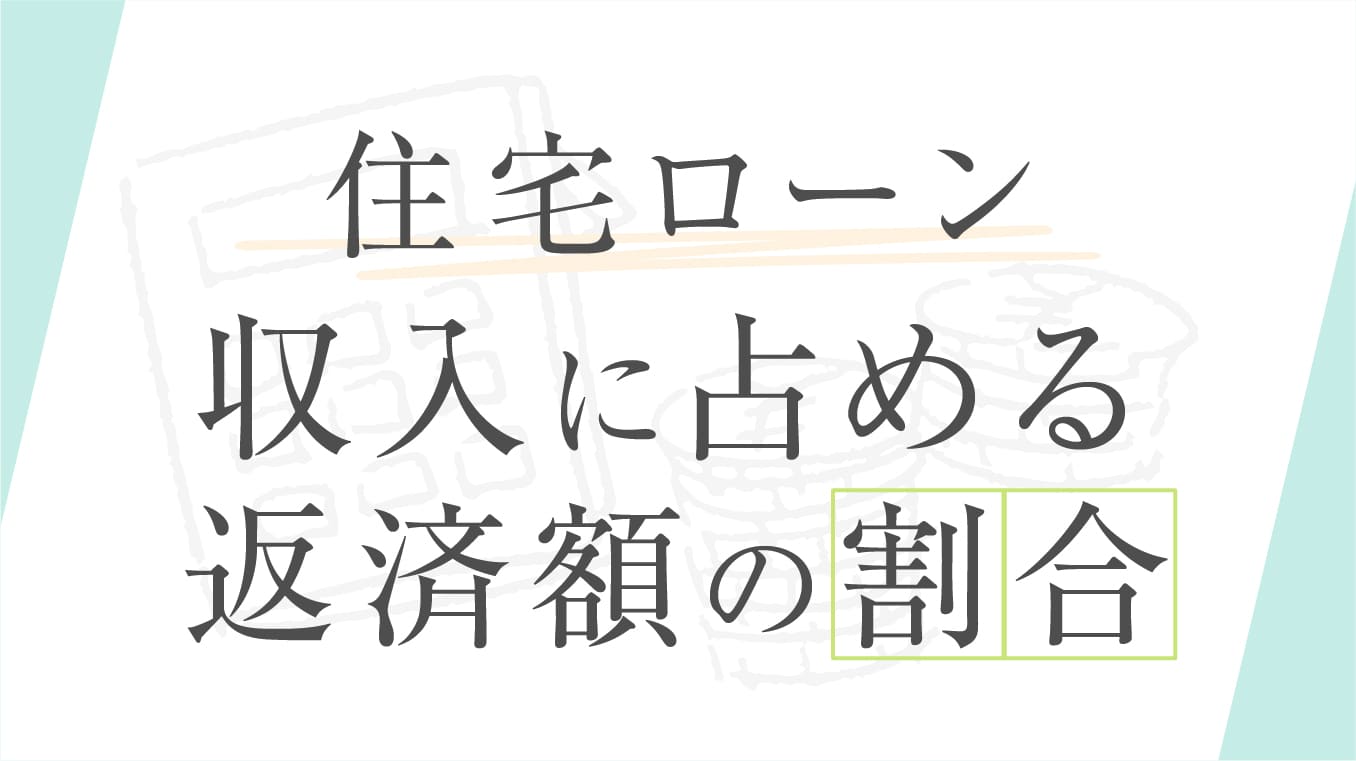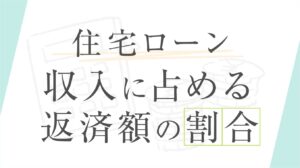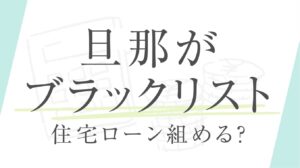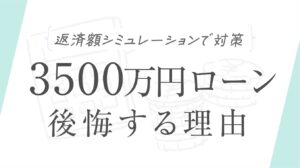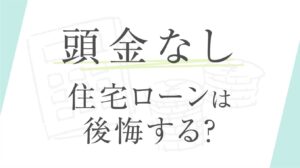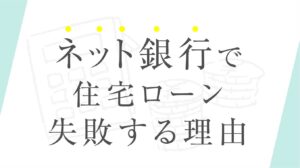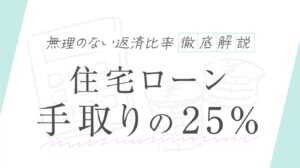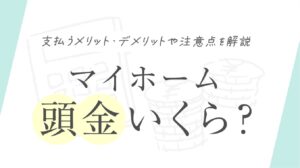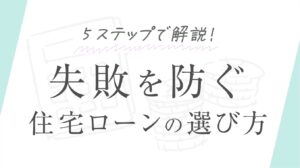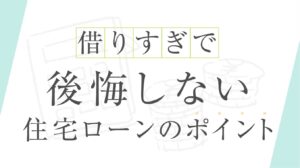「住宅ローンは収入の何割を返済に充てればいいの?」
「返済額は毎月いくら払う必要がある?借り入れ可能額を知りたい!」
「できるだけ毎月支払う額を抑えたい!」
 あき
あき住宅ローンで毎月支払う額によっては日常生活にも影響が出るので、できるだけ返済額を把握してから家を購入したいですよね!
この記事では、ハウスメーカーの営業職を15年以上担当した観点から、以下の内容を解説します。
- 住宅ローンの収入に占める返済額の割合「返済比率」の概要
- 年収ごとに借り入れられる金額
- 返済比率を抑える方法
- 返済に苦労しないための方法
ご自身の年収で快適に暮らしつつ、将来問題なく完済できる金額を把握できますので、ぜひ参考にしてみてください!
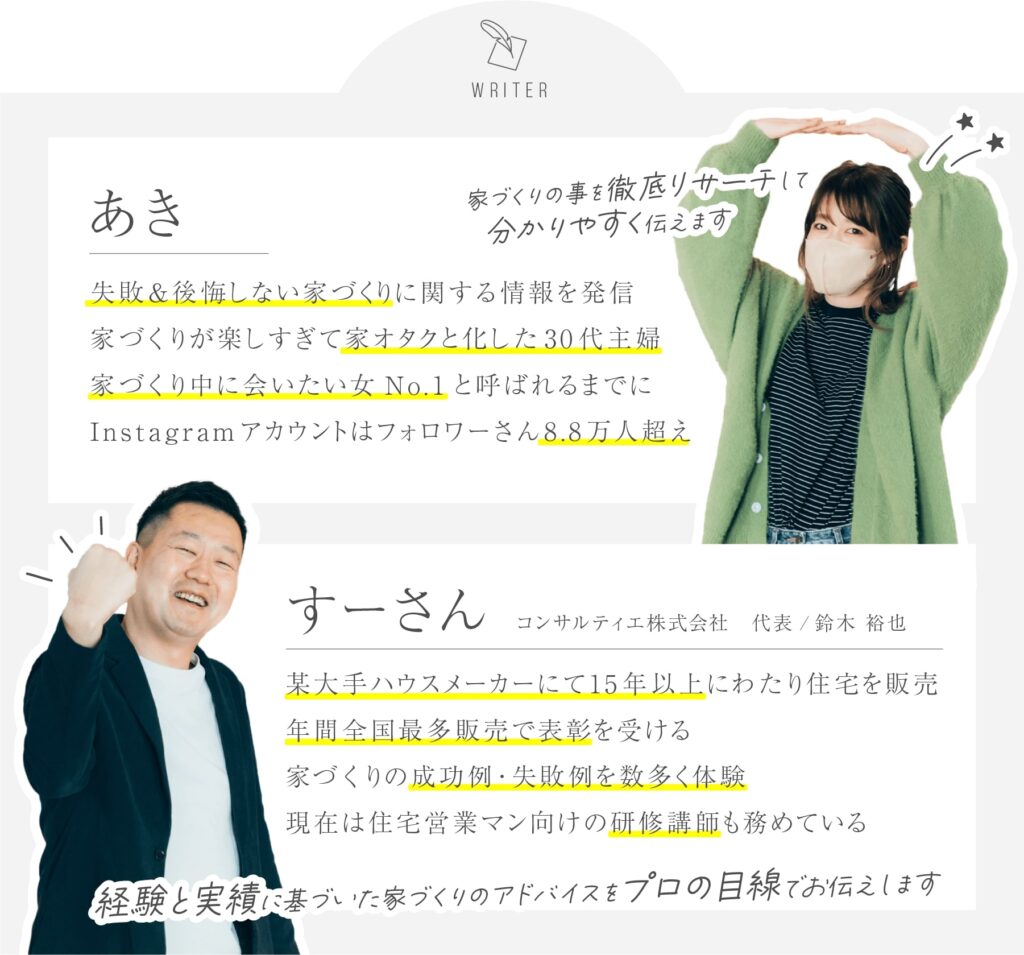
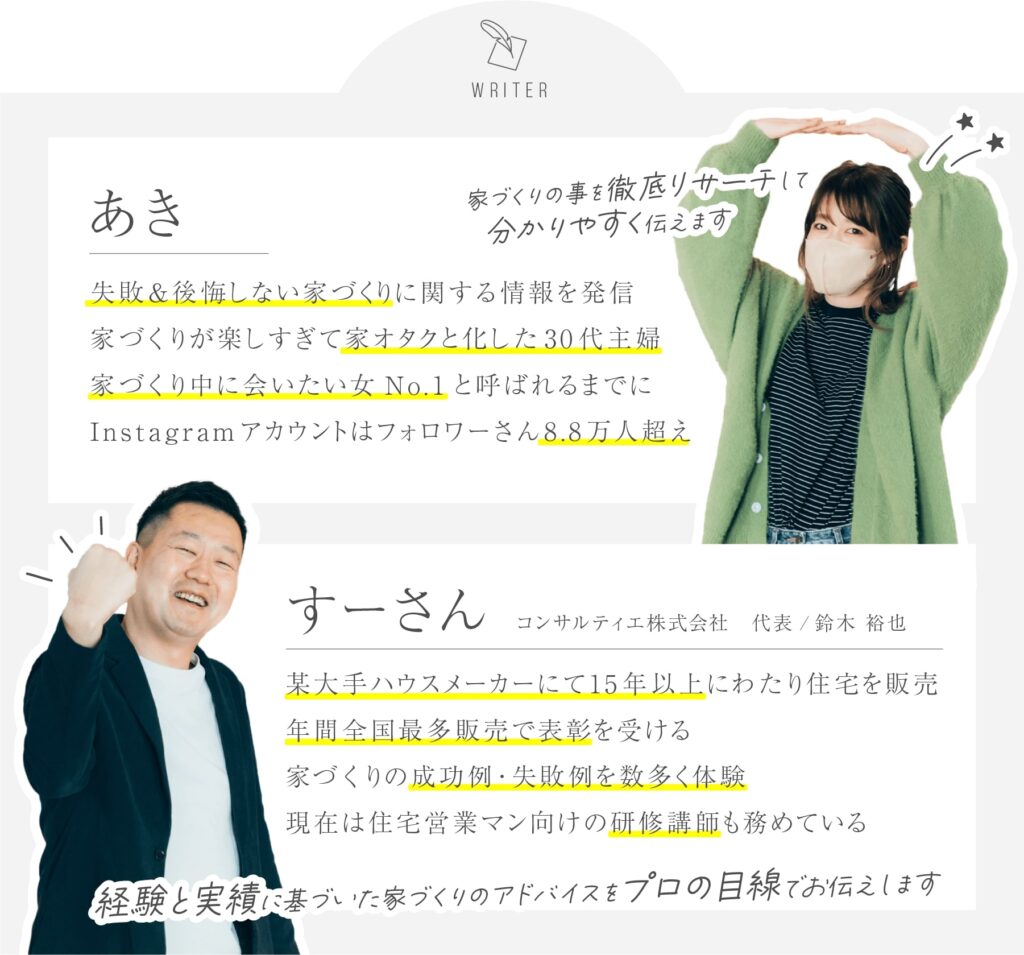
住宅ローンの収入に占める返済額の割合「返済比率」の概要
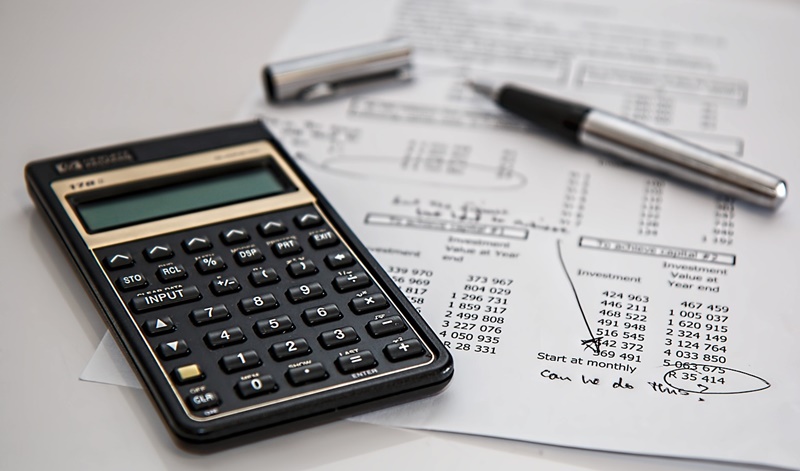
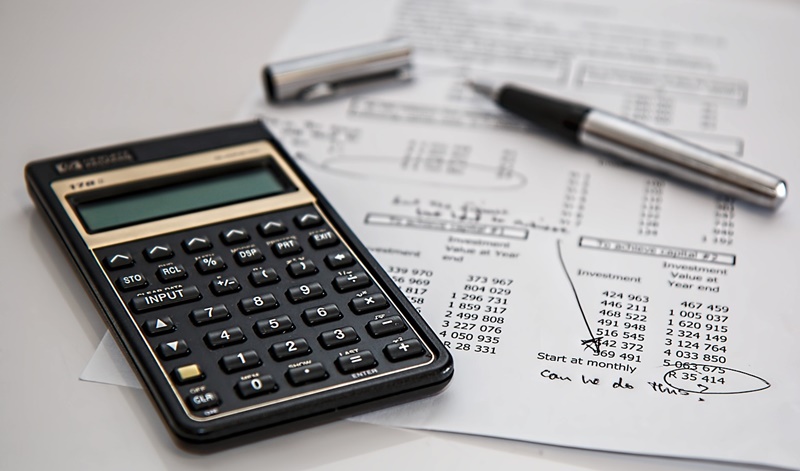
住宅ローンの収入に占める返済額の割合を表す指標として「返済比率」があります。別名で返済負担率とも呼ばれており、計算式は以下のとおりです。
返済比率(返済負担率)=年間返済額÷額面年収



手取りではなく、1年間にもらった給与の総支給額である「額面年収」で計算します!
たとえば、年収600万円の人が年間150万円で家を返済すると、返済比率は25%です。
ローンを組む人が、問題なく生活を送りながら返済できるかどうかの指標として重要視されています。
返済比率の目安や平均値
返済比率は無理なく返済できるよう、手取り収入の20%未満がよいとされています。



手取りの年収が800万円の場合、160万円以下に抑えるとよいということですね!
「令和4年度 住宅経済関連データ」によると、手取り月収や毎月の返済額の平均は、以下のような数値になっていることがわかりました。
- 手取り月収の平均値:556,998円
- 毎月の返済額の平均値:91,071円
- 返済比率の平均値:16.4%



平均値を見ていると、ほとんどの人が無理なく返済できるようローンを組んでいますね!
ただし、注文住宅の場合は月に約116,000円返済しているというデータがあり、返済比率を計算すると20.8%とやや高くなっています。
返済比率の上限
返済比率は金融機関や融資条件によって異なりますが、25%~35%が基準として設定されている場合が多いです。
金融機関では、返済能力を超えて融資することを防ぐために、条件を設けていることがほとんどです。



基準を超える返済比率を設定すると審査にとおらなくなってしまいます!
年収によっても返済比率の上限が決まっています。
たとえば、住宅金融支援機構の返済ローン「フラット35」を利用する場合、返済比率の上限値は以下のとおりです。
- 額面年収400万円以下:30%
- 額面年収400万円以上:35%
上限値に設定してもとおらないことがあるので、低くすることも考えましょう。
なお、住宅ローンの選び方については、関連記事「【後悔しない】初心者に最適な住宅ローンの選び方5ステップ!失敗を防ぐポイントも紹介」で解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
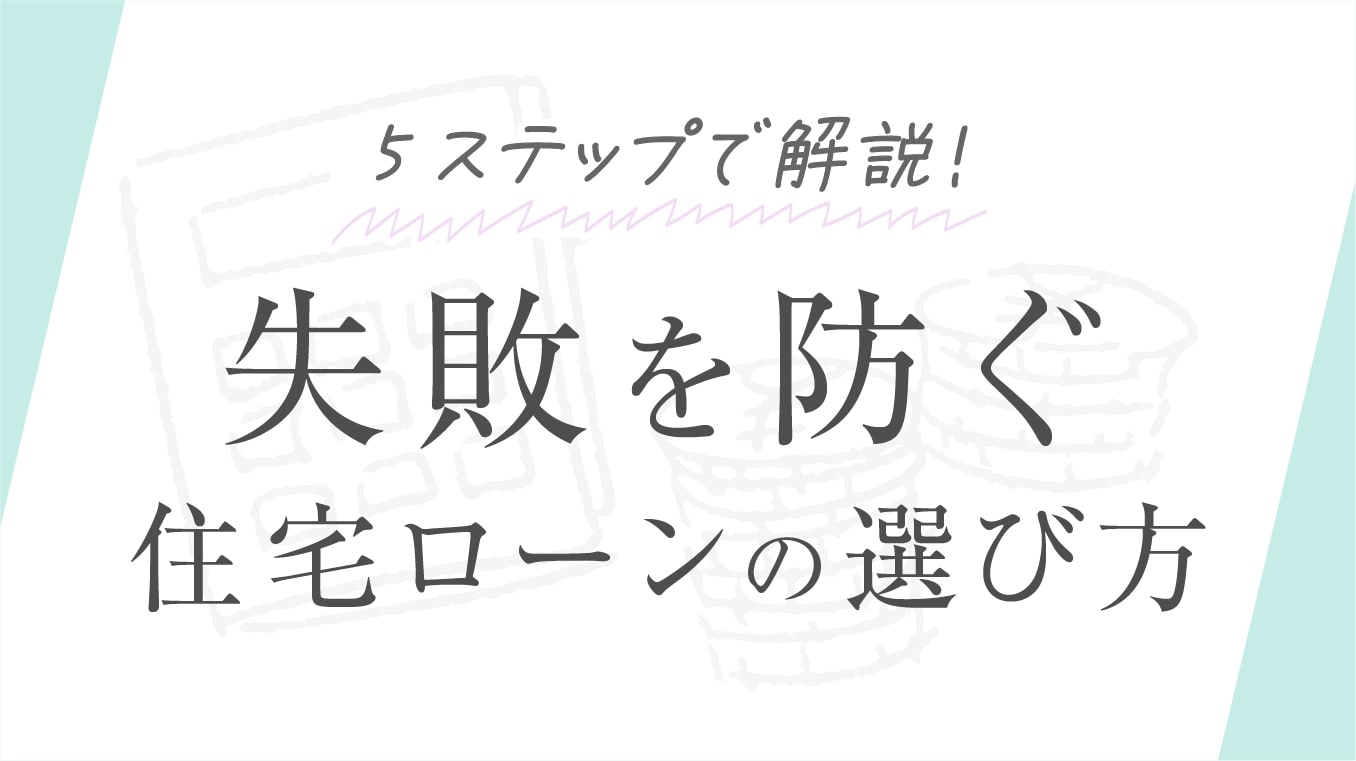
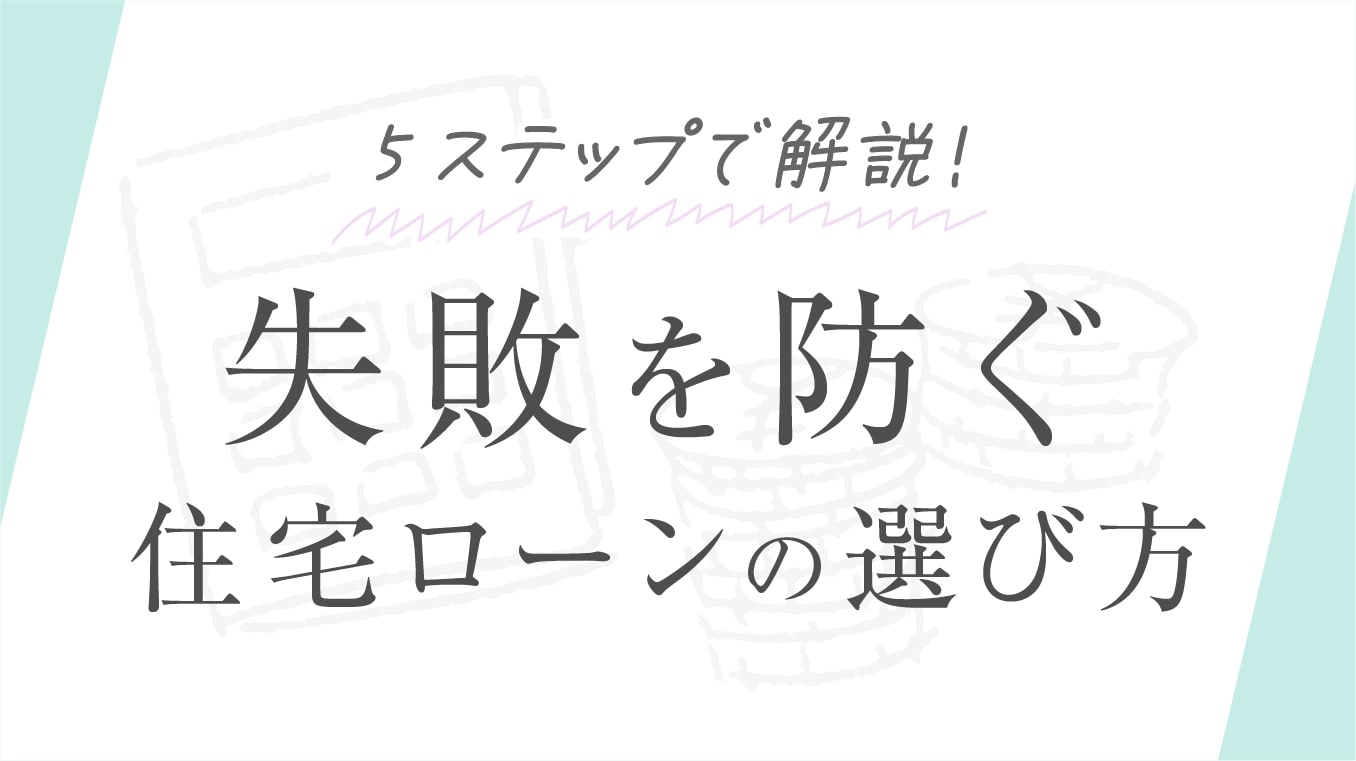
【年収別】住宅ローンに占める返済額の割合と借り入れ可能額の目安


借り入れ可能額=年間返済可能額 ÷ 12ヶ月 ÷ 100万円あたりの月返済額 × 100万
年間返済可能額=額面年収×返済比率



100万円あたりの月返済額は金利と借り入れ期間によって決められています!
たとえば、金利が1%で返済期間が35年の場合は2,823円です。借り入れ期間が短く、金利が高いほど100万円あたりの月返済額が高くなります。
ここでは、以下の条件における借り入れ可能額を年収別で紹介します。
- 年収:400万円~1,000万円(200万円ずつ紹介)
- 返済比率:20%~35%(5%ずつ紹介)
- 返済期間:35年
- 金利:1%
- 100万円あたりの月返済額:2,823円
- 返済方法:元利均等返済
自身の年収でどれくらい借り入れられるかおおよその金額を把握できるので、ぜひ参考にしてみてください!
1. 年収400万円の場合
| 返済比率 | 年間返済額 | 月間返済額 | 借り入れ可能額 |
|---|---|---|---|
| 20% | 80万円 | 6.7万円 | 2,362万円 |
| 25% | 100万円 | 8.3万円 | 2,952万円 |
| 30% | 120万円 | 10.0万円 | 3,542万円 |
| 35% | 140万円 | 11.7万円 | 4,133万円 |



35年でローンを組むことで返済比率が20%でも2,300万円以上の借り入れが望めます!
2. 年収600万円の場合
| 返済比率 | 年間返済額 | 月間返済額 | 借り入れ可能額 |
|---|---|---|---|
| 20% | 120万円 | 10万円 | 3,542万円 |
| 25% | 150万円 | 12.5万円 | 4,428万円 |
| 30% | 180万円 | 15万円 | 5,313万円 |
| 35% | 210万円 | 17.5万円 | 6,199万円 |
返済比率20%でも3,500万円以上借りられるので、30坪2階建ての一軒家を建てるのには充分です。
3. 年収800万円の場合
| 返済比率 | 年間返済額 | 月間返済額 | 借り入れ可能額 |
|---|---|---|---|
| 20% | 160万円 | 13.3万円 | 4,723万円 |
| 25% | 200万円 | 16.7万円 | 5,904万円 |
| 30% | 240万円 | 20.0万円 | 7,085万円 |
| 35% | 280万円 | 23.3万円 | 8,265万円 |



返済比率20%で4,700万円以上、35%であれば8,200万円と、土地の取得と一軒家の建設ができるくらいの金額を借り入れる可能性があります!
4. 年収1,000万円の場合
| 返済比率 | 年間返済額 | 月間返済額 | 借り入れ可能額 |
|---|---|---|---|
| 20% | 200万円 | 16.7万円 | 5,904万円 |
| 25% | 250万円 | 20.8万円 | 7,380万円 |
| 30% | 300万円 | 25.0万円 | 8,856万円 |
| 35% | 350万円 | 29.2万円 | 1億332万円 |
年収1,000万円の人であれば、場所や設備に突出したこだわりがない限り、快適に住める家を購入できるほどの金額を借り入れられます。



借り入れ可能額について詳しく知りたい方は、すーさんにも相談してみましょう。
すーさんの相談窓口は、住宅選びやローンの組み方など、あなたが家づくりで悩んでいることについて解決できるサービスです。
ハウスメーカーの営業職を15年以上した経験から、一人ひとりに最適な住宅ローンについても紹介していますので、お気軽にお問い合わせください!
\ ノープランでOK /
住宅ローンの収入に占める返済額の割合を抑える3つの方法


できるだけ生活に余裕を持たせながら返済できるよう、返済額の割合を抑える方法を3つ紹介します。
- 頭金を増やす
- 返済期間を長くする
- ほかのローンを返済しておく
借り入れ可能額を減らすことで返済への不安をやわらげられますので、ぜひ試してみましょう。
1. 頭金を増やす
頭金を増やすことで、借り入れ金額自体が少なくなり返済比率を抑えられます。



利息も減り、金融機関の適用金利が下がる可能性が高いです!
ただし、自己資金をすべて使わないように注意しましょう。子どもの学費やほかの建設に関わる費用などを支払えなくなってしまうためです。
頭金の詳細は関連記事「【貯金0はNG】マイホームの頭金は住宅価格の1〜2割が目安!支払うメリット・デメリットや注意点を解説」で紹介しています。あわせてお読みください!


2. 返済期間を長くする
20代くらいの人であれば、返済期間を長くすることで返済比率を抑えられます。
ただし、金利によっては総返済額が高くなるので注意が必要です。とくに30~40代の場合は負担額が重くなるので気を付けましょう。



返済期間の延長はあくまで最終手段として検討してみてください!
3. ほかのローンを返済しておく
返済比率は1年間で支払うすべての返済額から算出されるため、できるだけほかの返済ローンをなくしましょう。
ローンの返済の種類として、主に以下のようなものがあります。
- クレジットのリボ払い
- スマホの分割払い
- カーローン
- 奨学金の返済



これらが残っている場合は早めに返済することをおすすめします!
返済比率が高くなってしまうと、住宅ローンを借りられなくなる可能性あるので気を付けましょう。
住宅ローンの返済に苦労しないための7つのポイント


住宅ローンを組むときや返済途中で苦労することがないよう、以下の7点に注意が必要です。
- 家計が圧迫されないようにする
- 65歳で完済することを意識する
- 繰り上げ返済を活用する
- 条件のよい人ほど借りすぎないようにする
- 個人事業主は所得で判断する
- 金利タイプや返済方法も考慮する
- 適用金利と審査金利について理解する
住宅ローンを完済するためのコツを把握できますので、返済に不安のある方はぜひご覧ください。
なお、住宅ローンの不安を解消する方法は関連記事「【不安解消】住宅ローンを心配しすぎてしまう人必見!5つの対策や組み方のコツを紹介」で詳しく解説しています。あわせてお読みください!
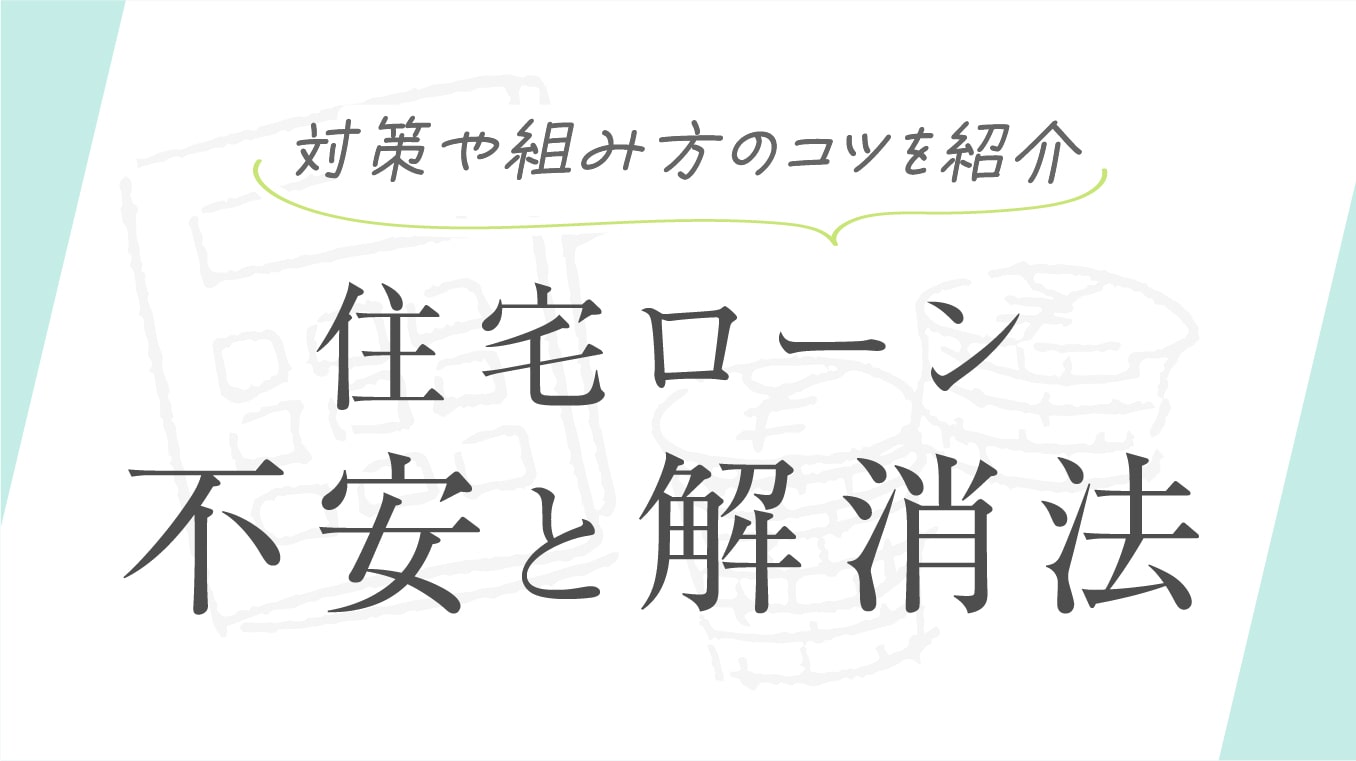
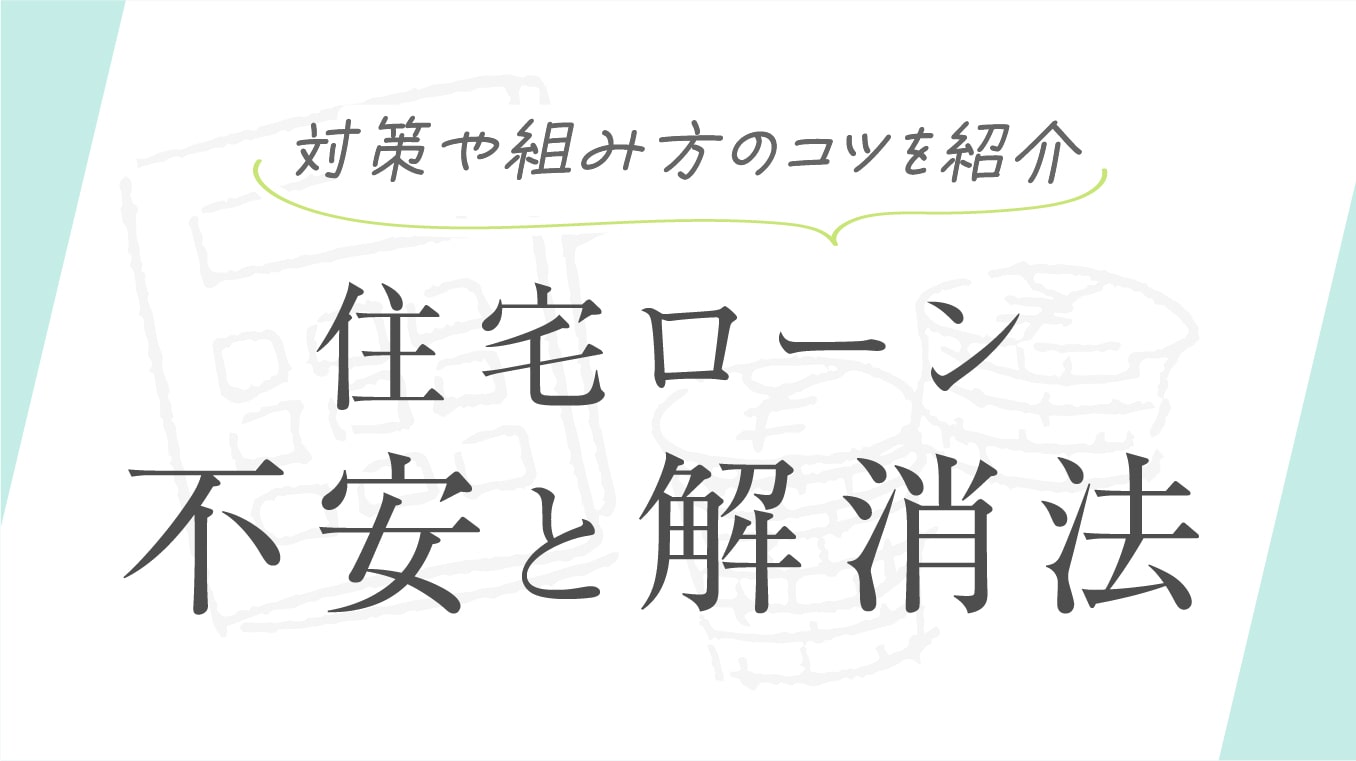
1. 家計が圧迫されないようにする
返済比率を高くしすぎると、家計が圧迫してしまうので注意しましょう。



子どもの学費や教育費、老後の資金などしっかりマネープランを考えてローンを組むことが大切です!
35%や40%に設定すると返済に苦しむリスクが高まるので、20%以下にしましょう。
2. 65歳で完済することを意識する
現在、定年退職をきっかけに住宅ローンで自己破産する人がいます。
とくに年金がもらえるかどうかも怪しいご時世になっているため、これから家を建てようと考えている方は細心の注意が必要です。
厚生労働省の「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」データによると、月にもらえる年金は以下のようになっています。
- 厚生年金:月額約14万円
- 国民年金:月額約5万5,000円
厚生年金でも最低限暮らしていける金額しかもらえないので、仮に返済額が月10万円だとしたら生活が苦しくなります。



返済が終わっていないと定年退職後も働かなければならないので、働いているうちに完済するようにしましょう!
3. 繰り上げ返済を活用する
できるだけ早期に完済できるよう、繰り上げ返済の活用がおすすめです。



今後返済する予定の金額を先に支払うことで利息額を軽減できます!
総返済額が低くなり、完済までの時間も短縮できるので、老後の資金に充てられるようになります。
4. 条件のよい人ほど借りすぎないようにする
大企業で働いている人や公務員は安定した年収が得られることで、銀行側がお金を貸したがってしまうので注意が必要です。



返済比率が40%でも貸してくれるので、つい借りたくなるかもしれません!
ただし、手取りに対しての負担率が50%超えると生活に支障をきたすリスクがあります。
最悪の場合、貯金ができず子どもの学費を払えなくなる事態も起きるかもしれません。



「借りられる金額」よりも「返せる金額」を意識してローンを組むことが大切です!
また、借りすぎて後悔しないポイントについては関連記事「【要チェック】住宅ローンの借りすぎで後悔しない7つのポイント!借り入れ額の目安や対処方法を解説」で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
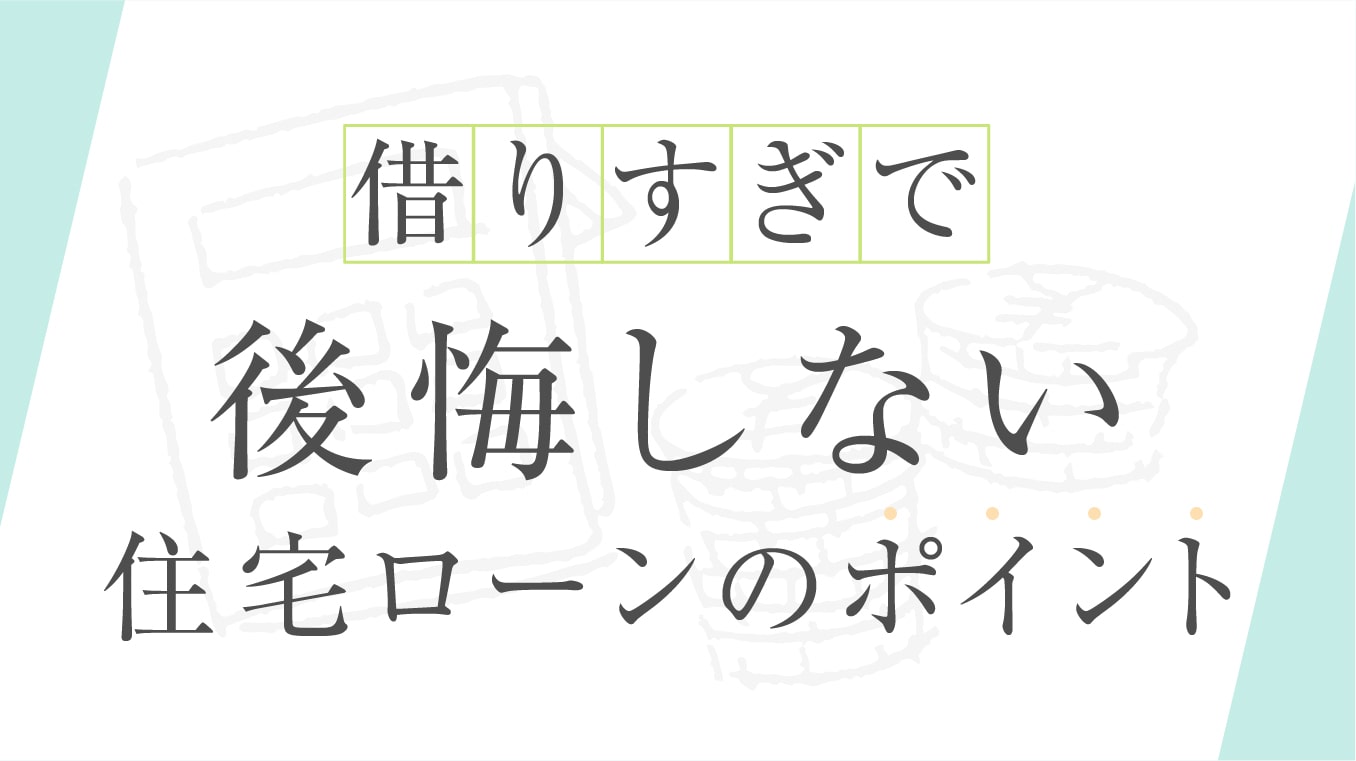
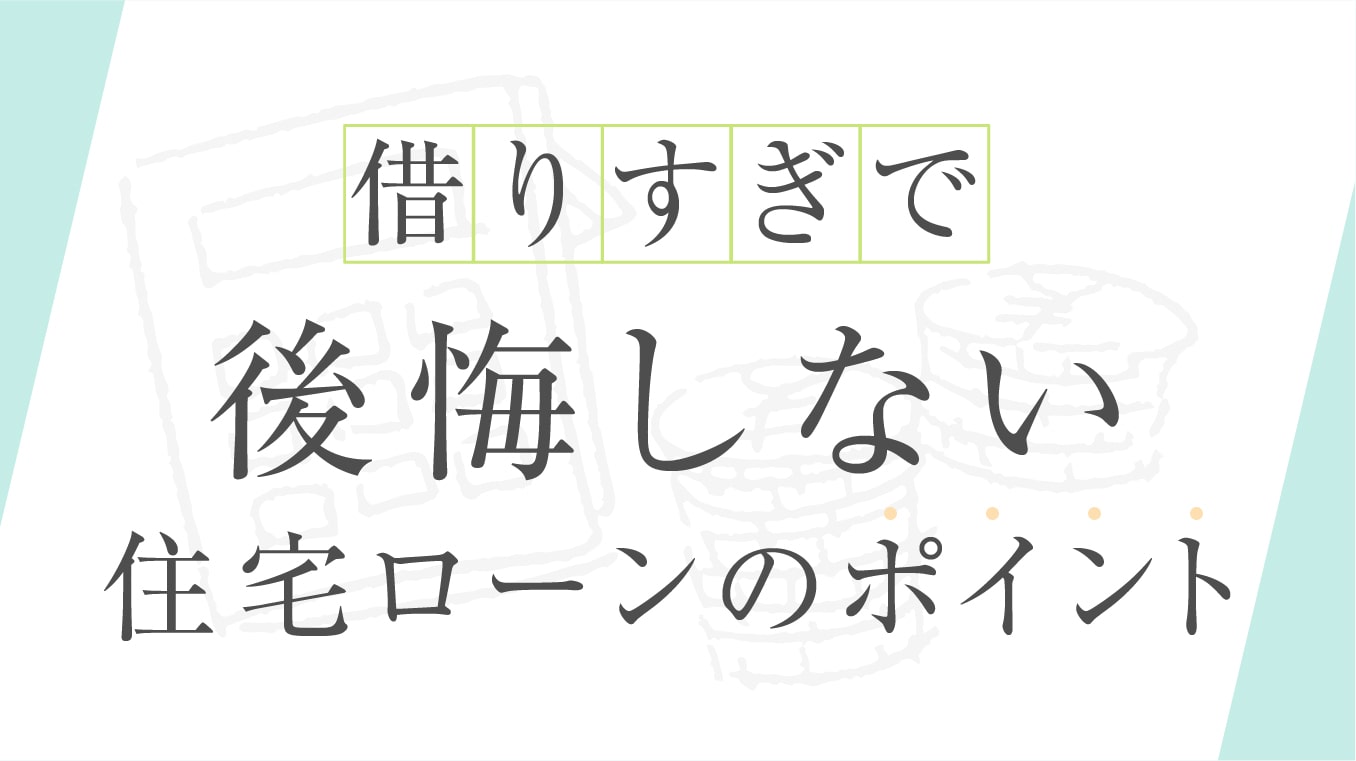
5. 個人事業主は所得で判断する



個人事業主の場合は一般的な社会人の年収で計算できないため、確定申告書の所得で判断しましょう!
所得は売上から経費を差し引いた利益のことです。売上が高くても経費が多すぎれば所得が低くなります。
所得が低い場合や赤字が出た場合は、住宅ローンの審査で不利になる場合もあります。
また、安定的に収入を得られない個人事業主と会社員の返済比率の考え方は異なり、審査にも影響する可能性があるので注意が必要です。
6. 金利タイプや返済方法も考慮する
- 固定金利型:金利が一定のローン
- 変動金利型:定期的に金利が変動するローン
- 固定金利期間選択型:金利を固定か変動かを選べるローン
金利タイプによって総返済額が変動します。



将来設計を立てやすいのは、固定金利型です!
また、返済方法については、元利均等返済と元金均等返済の2種類があります。
元利均等返済は元金+金利を一定額支払い続ける方法で、元金均等返済は元金だけが一定で金利が徐々に減っていく返済方法です。
前者は一定金額で支払いたい人、後者は元金を早く減らして金利を減らしたい人におすすめします。
7. 適用金利と審査金利について理解する
適用金利と審査金利を把握することで、借り入れ限度額を調整できます。



適用金利は実際に適用される金利で、審査金利は審査で使われる金利のことです!
適用金利が上がると返済額が大きくなってしまうため、審査ではあえて金利を高くして無理な借り入れを防止しています。
金利の種類によって借り入れ可能額や返済額が変わるため注意が必要です。
住宅ローンは収入に占める返済額の割合で決めよう


住宅ローンは収入に占める返済額の割合が20%以下に抑えましょう。20%以下にすることで、暮らしに必要な資金を確保しつつ、滞りなく返済できるようになります。
年収や金利、返済比率などによって借り入れ可能額が異なるので、住宅ローンの会社に算出してもらってから審査を依頼しましょう。
返済に苦しまないよう、家計やライフプランを考慮して、最適な住宅ローンを組んでみてください。



ローンの組み方や返済に不安な人は「すーさんの相談窓口」がおすすめです!
「すーさんの相談窓口」では、家づくりに関するお悩みに対して最適な解決方法を提案しています。あなたの年収に合った住宅ローンの組み方についてもお答えしますので、お気軽にご相談ください。