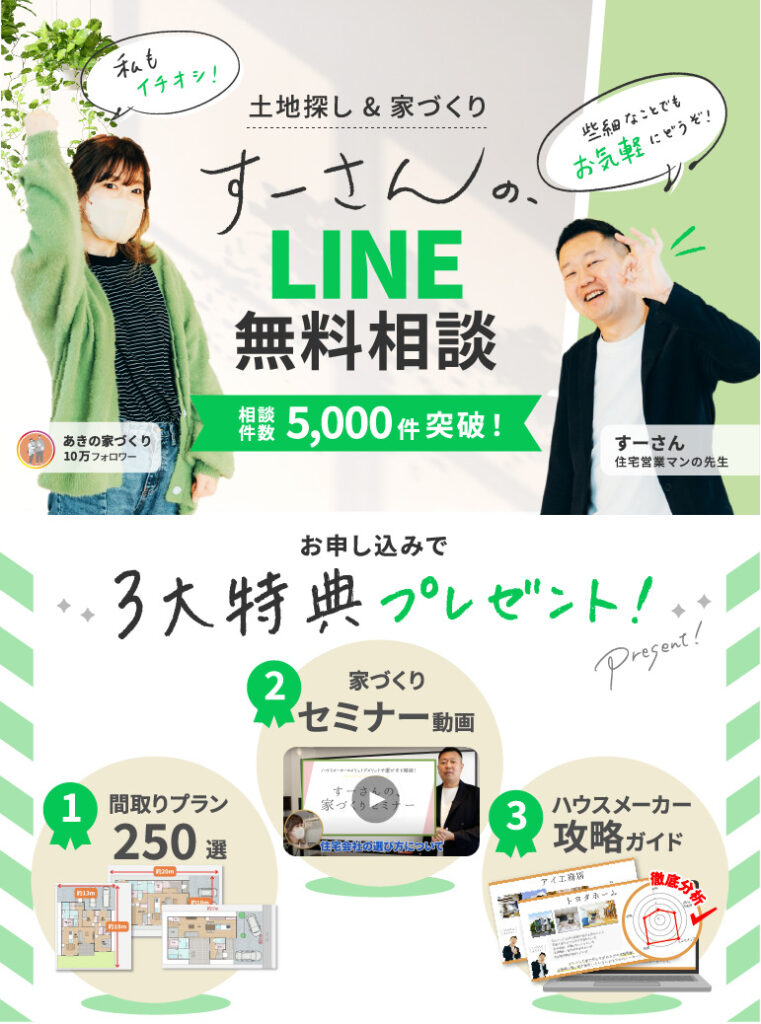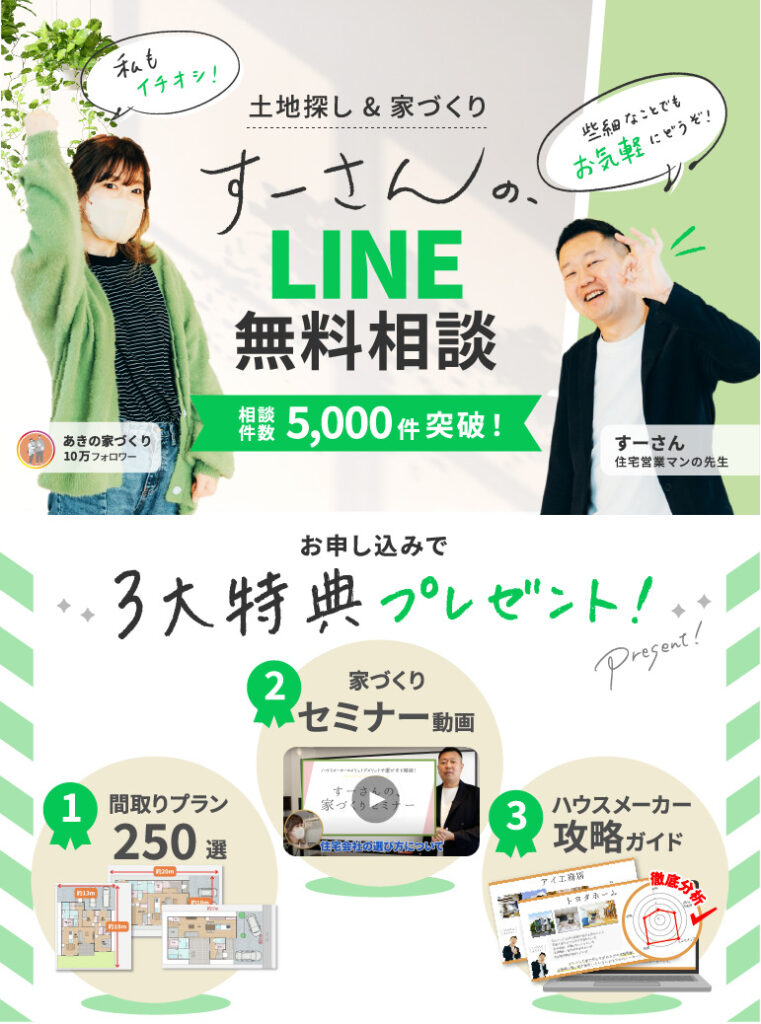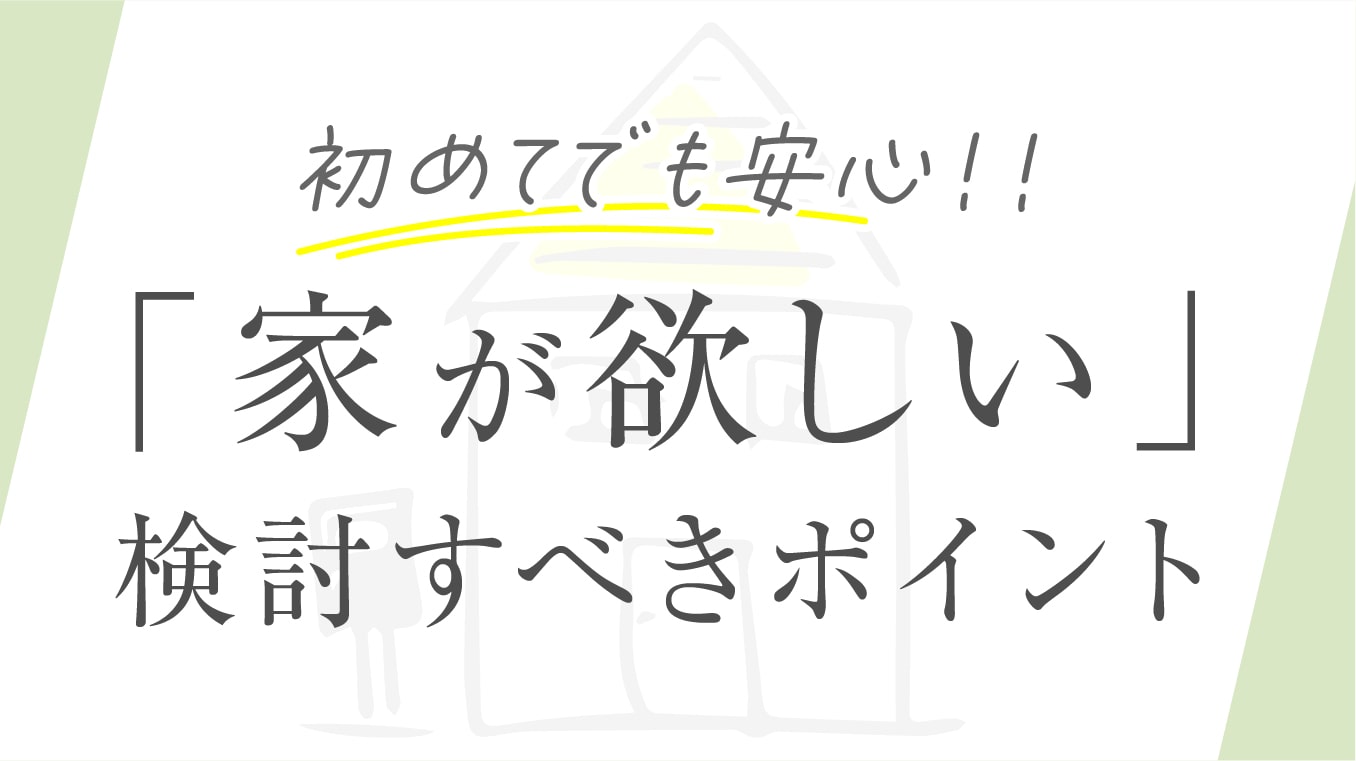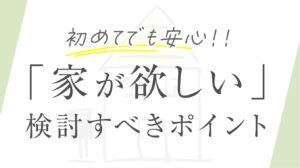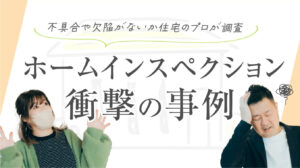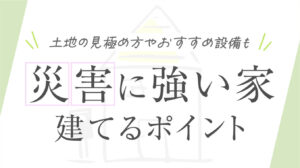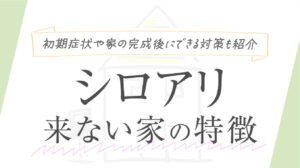「家が欲しいときはまず何から手を付ければ良い?」
「年齢が50歳を超えているので、住宅ローンを組めるのか心配」
「どの程度の年収があれば住宅ローンを組めるのか知りたい」
家が欲しいと考えている方のなかには、購入の手順や住宅ローンの契約に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
家を購入する経験は人生に多くあるわけではないため、わからないことが多くても当然です。
この記事では、家の購入について以下の内容を解説します。
- 家が欲しいときに検討するポイント
- 【新築・中古別】家の購入手順
- ローンが組めないときの解決策
- 50歳を超えている場合の対処方法
- 家を買うべきでない人の特徴
 あき
あき知識がまったくない方でも理解できる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください!
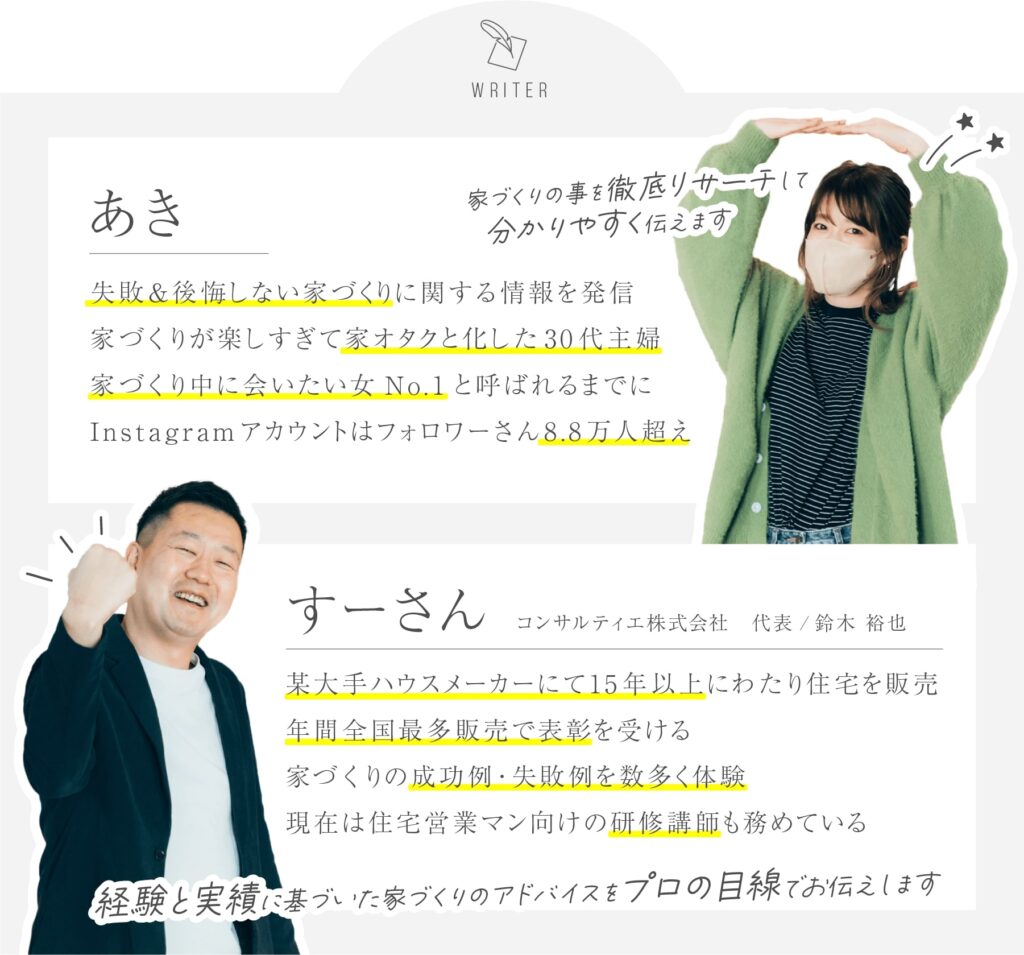
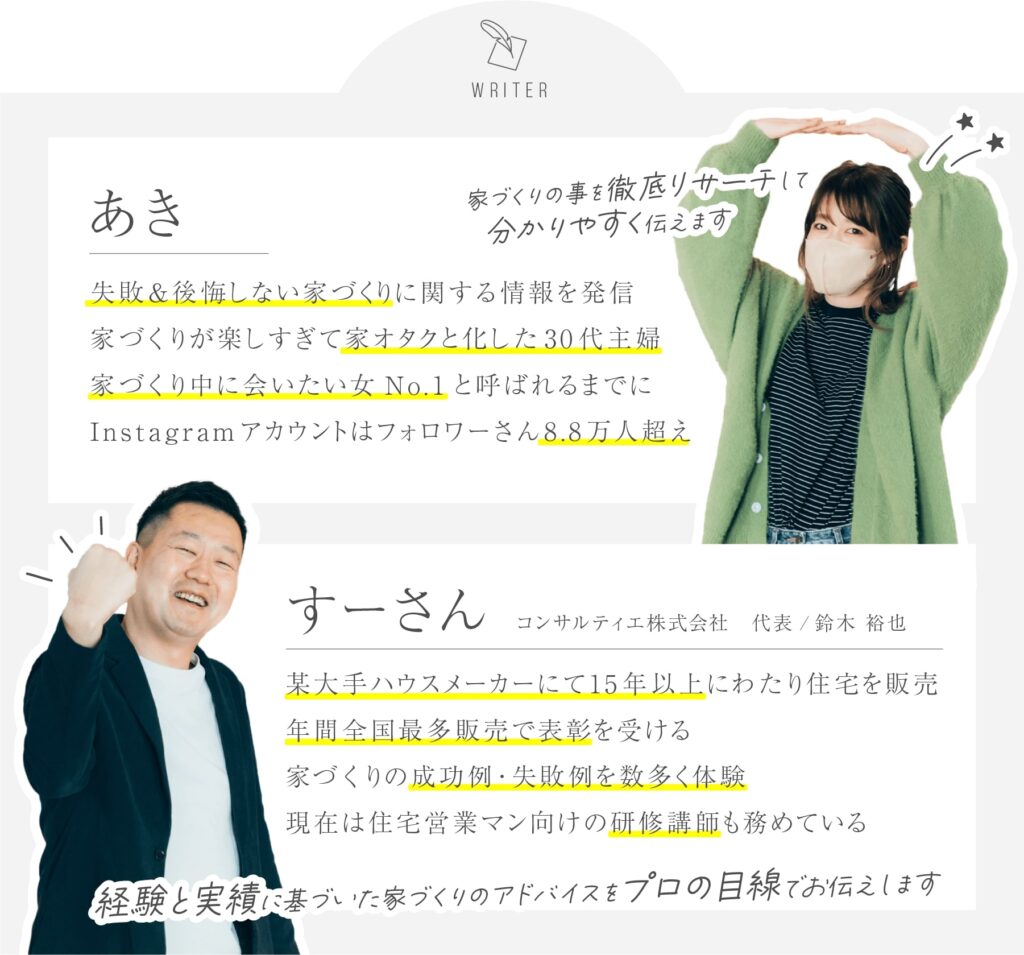
家が欲しいときにまず検討する7つのポイント


家が欲しいときには、ハウスメーカーに相談する前に、まず以下の7つの項目について検討しましょう。
- 購入するタイミングを決める
- 予算を立てる
- 新築か住宅か選ぶ
- 戸建てかマンションか選ぶ
- 戸建てなら注文住宅か建売住宅にするかを選ぶ
- 立地を検討する
- 諸経費を計算しておく
仮の方針が立っているだけで、その後の段取りを進めやすくなります。



まずはご家族と話し合って、希望を出し合ってみてください!
1. 購入するタイミングを決める
家を購入する際には住宅ローンを組む方が多いでしょう。そのため、ローンの借り入れ額と返済期間を明確にして、購入のタイミングを検討する必要があります。
国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によると、住宅を購入した人の平均年齢は以下の通りです。
| 住宅の種類 | 世帯主の平均年齢 |
|---|---|
| 注文住宅 | 39.5歳 |
| 建売住宅 | 37.5歳 |
| 新築マンション | 39.9歳 |
| 中古一戸建て住宅 | 43.6歳 |
| 中古マンション | 43.7歳 |
※1次取得者(初めて住宅を取得した世帯)のデータを参照
データによると、住宅を購入者の平均年齢は「30歳後半~40歳前半」が多いことがわかります。



住宅ローンの返済最長期間は35年で契約したいと考えているなら、少しでも若いうちに購入しておくと安心です!
また、ライフイベントから購入のタイミングを考えるのもおすすめです。例えば、以下のようなライフイベントの際に検討するといいでしょう。
- 結婚したとき
- 子どもが生まれるとき
- 子どもが入園、進学するとき
- 子どもが独立するとき
- 自身が定年退職するとき



どのようなタイミングで購入するか家族で話し合う必要がありますね!
2. 予算を立てる
国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査報告書」によると、住宅を購入した際の平均世帯年収と平均購入資金は以下の通りです。
| 物件の種類 | 平均世帯年収 | 平均購入資金 |
|---|---|---|
| 注文住宅 | 731万円 | 4,713万円 |
| 建売住宅 | 722万円 | 4,074万円 |
| 新築マンション | 923万円 | 5,048万円 |
| 中古一戸建て住宅 | 682万円 | 3,025万円 |
| 中古マンション | 609万円 | 2,943万円 |
※1次取得者(初めて住宅を取得した世帯)のデータを参照
注文住宅の購入を検討している方は、5,000万円程度かかることを想定しておく必要があります。



中古住宅でも、3,000万円程度を用意する必要がありそうですね。
また、予算を立てる際には、住宅ローンの借り入れ額をシミュレーションしておきましょう。家を購入した後に、教育資金やメンテナンス費用が必要になり、ローン返済が困難にならないかを想定しておくと安心です。
なお、住宅ローンのシミュレーションについては、モゲチェックを活用するのがおすすめです!金利が0.1%でも下がれば総支払額が数百万円も変わることがあるため、複数の金融機関を比較しておきましょう。
モゲチェックの詳細は、関連記事「【金利0.1%の差が命取り】住宅ローンの負担を下げるにはモゲチェックがおすすめ!使い方をわかりやすく解説」で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください!


3. 新築か中古か選ぶ
新築か中古を選ぶ際には、住宅の価格だけでなく、多面的に検討することが大切です。新築を選ぶメリットは主に、以下の5つです。
- 間取りやデザインを決められる
- 最新の設備が整っている
- リフォーム費用や当面の修繕費がかからない
- 税金が優遇される
- 保証期間が長い
新築は住宅の設計に携われるため、より理想の家を実現しやすいといえます。また、耐震性や高断熱などの最新の設備を取り入れられます。



固定資産税といった税金の減免措置を受けられる点も、大きなメリットといえますね!
一方、中古を選ぶメリットは、主に以下の3つです。
- 住宅価格が安い
- 立地面での選択肢が多い
- 下見ができる
経過年数に応じて住宅の価値は下がるため、中古住宅は価格が安い傾向にあります。また、住みたいエリアで物件を探すことが可能です。
4. 戸建てかマンションか選ぶ
マンションは立地が良いケースが多く、好立地の物件は戸建てよりも価格や資産価値が高くなります。
戸建てのメリットは、主に以下の3つです。
- ライフスタイルの自由度が高い
- 住宅が広い
- 税金や管理費がマンションよりも安い
また、マンションに比べて住宅面積が広いため、人数が多い家庭では戸建てのほうが暮らしやすいと感じるでしょう。



戸建ては集合住宅であるマンションに比べると、他人を気にせずに生活できることがメリットですね!
一方、マンションのメリットは以下の3つです。
- 立地が良い物件が多い
- 生活の利便性が高い
- 住み替えやすい
マンションの良さは、立地面や利便性の高さです。「ゴミを24時間いつでも捨てられる」「共用部の管理や掃除を任せられる」など、生活の負担を軽減できます。



夫婦2人暮らしのように、世帯人数の少ない家族の場合、マンションのほうが生活しやすいかもしれませんね!
戸建てとマンションの違いやそれぞれの詳細は、関連記事「【徹底比較】持ち家を買うならマンションと一戸建てどっち?価格・住みやすさ・選び方を解説」で解説しています。ぜひこちらも参考にしてみてください!
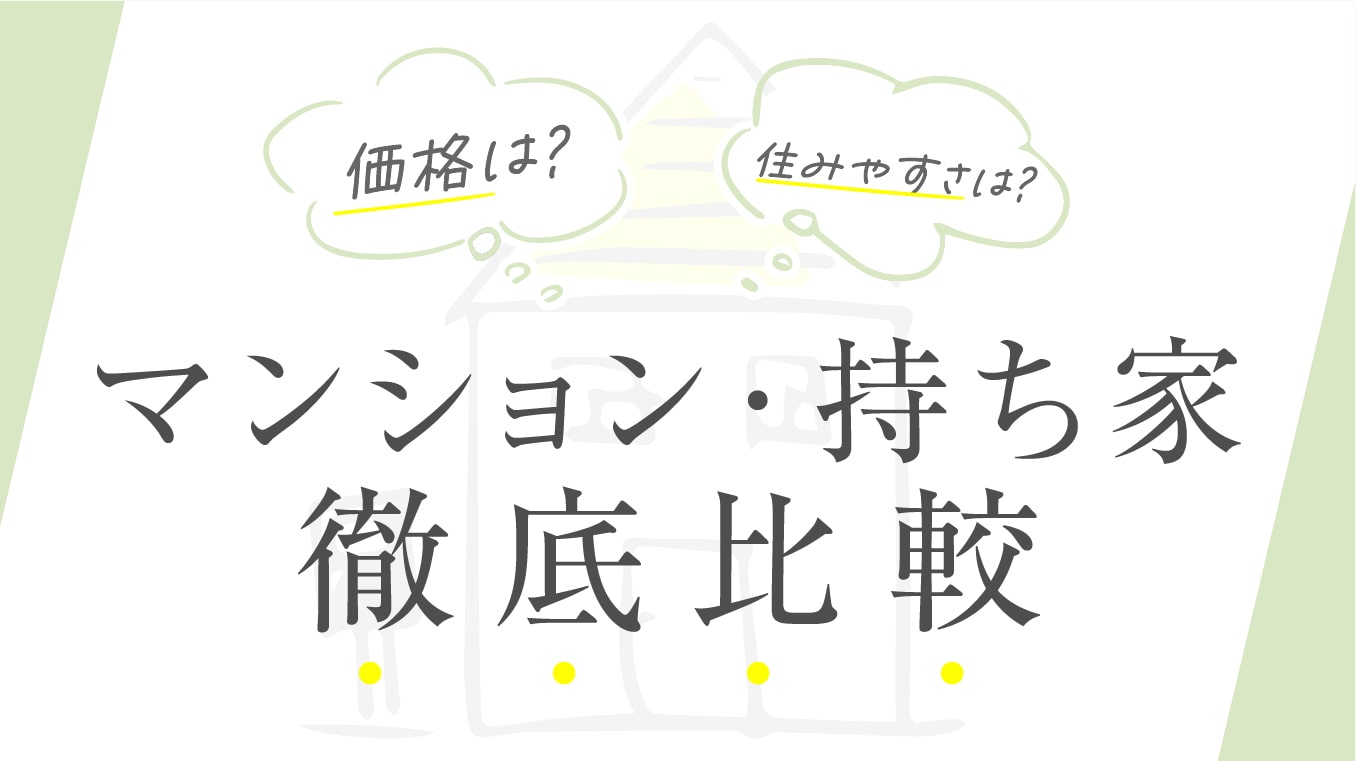
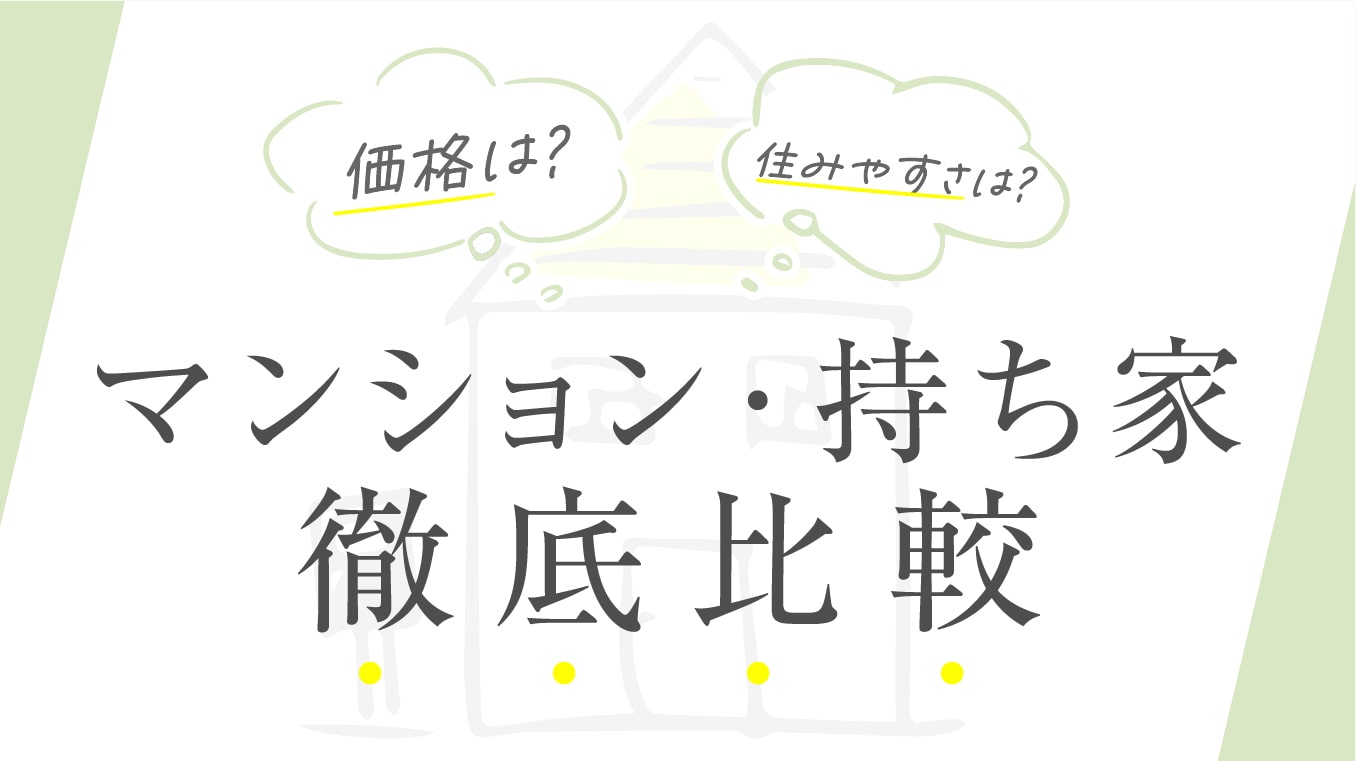
5. 戸建てなら注文住宅か建売住宅にするかを選ぶ
注文住宅とは、土地選びや間取りなどの家に関する内容を、自由に決められる一戸建てのことです。一方、建売住宅は、ハウスメーカーなどの規格プランに従って建築された一戸建てのことです。



理想の住宅を建てたい人には、注文住宅がおすすめです!
ただし、注文住宅は建売住宅を比較して、価格が高い点には注意が必要です。
6. 立地を検討する
注文住宅を建てる際、土地探しから始める人は、立地を十分に検討する必要があります。



住宅を建てた後の生活をイメージして立地を選びましょう!
立地を決める際の判断基準は以下のようなポイントがあります。
- 生活する上での利便性(通勤・通学)
- 子育て環境(保育園、幼稚園、学校への距離)
- 商業施設までの距離や移動手段
- 治安
- 日当たり
- 方角
どのような環境で住みたいかをイメージして、立地を決めるようにしましょう。
7. 諸経費を計算しておく
家を購入する際には様々な諸経費がかかるため、事前に計算しておくと安心です。
物件購入時にかかる費用は以下のようなものがあります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 司法書士報酬
- 融資事務手数料
物件の種類ごとの諸経費目安は以下の通りです。
| 物件の種類 | 諸経費の目安 |
|---|---|
| 注文住宅 | 物件取得費の10~12% (土地を取得している場合は3~6%) |
| 建売住宅 | 物件取得費の6~9% |
| 新築マンション | 物件取得費の3~6% |
| 中古一戸建て | 物件取得費の6~9% |
| 中古マンション | 物件取得費の6~9% |



諸経費も高額なのでしっかりと計算しておく必要がありますね!
【新築・中古別】家が欲しいときの購入手順


家が欲しいけれど、何から始めたら良いかわからないという方は多いのではないでしょうか。



こちらでは、新築と中古それぞれの購入手順を解説します!
1. 新築住宅の場合
新築住宅の購入までの手順は、以下の8ステップです。
- カタログの取り寄せ
- 住宅展示場の見学
- 間取り設計の打ち合わせ
- 土地探し
- 見積もり作成・住宅ローン仮審査
- 工事請負契約・住宅ローン本審査
- 新築工事の着工
- 引き渡し・入居
新築の場合は、カタログや住宅展示場の見学などで、ハウスメーカーを選ぶところから始めます。ハウスメーカーの営業担当者が付けば、その後の段取りを丁寧にサポートしてくれるでしょう。



カタログの取り寄せには、LIFULL HOME’Sを活用するのがおすすめです!
複数のハウスメーカーに一括で請求できるため、効率的に情報収集ができます。また、家づくりの基本をまとめた「家づくりノート」がもらえるので、知識がなくて心配という方はぜひ活用してみてください。
LIFULL HOME’Sの家づくりノートの詳細は、関連記事「【めっちゃ簡単】家づくりに役立つノートをもらう方法!よくある疑問もスッキリ解決(PR)」で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください!


2. 中古住宅の場合
中古住宅の購入までのステップは、以下の通りです。
- 購入したい家の選定
- 購入の申込み
- ローンの事前審査
- 売買契約
- ローンの本審査
- 引き渡し・入居



中古住宅の場合、住みたい地域にある不動産屋で購入したい家を決めることがスタートです!
購入したい家が決まれば、申込み、ローン審査と手続きが進みます。ローンの事前審査に通った後には、売買契約を結びます。
家が欲しいけどローンが組めないときの解決策3選


住宅ローンの審査を受けたけれど通らなかったという方は、以下の3つの方法を試してみてください。
- 金融機関を変更する
- 担保や保証人を追加する
- 借り入れ額を減らす
一つひとつ見ていきましょう。
1. 金融機関を変更する



住宅ローンの審査基準は、金融機関によって異なります!
同じ条件であっても、金融機関を変えると審査に通ることがあります。
たとえば、地元への融資に積極的な地方銀行や信用金庫なども選択肢に入れると良いでしょう。
2. 担保や保証人を追加する
住宅ローンの審査では96.1%の金融機関が、担保評価を行っています。担保や保証人を追加することで、審査をパスできる可能性があります。



担保や保証人の追加は、返済能力が上がったと判断されるためですね!
3. 借り入れ額を減らす



年収や返済負担率が問題である場合、購入する物件を見直してから再審査を受けてみましょう!
自身の収入面に問題がある場合は、返済計画に無理があったと考えるべきです。
ローンの借り入れ額については、関連記事「【貯金0はNG】マイホームの頭金は住宅価格の1〜2割が目安!支払うメリット・デメリットや注意点を解説」で解説しています。ぜひこちらも参考にしてみてください!


家が欲しいけど50歳を超えている場合の対処方法3選


家の老朽化や家族構成の変化などから、50歳を超えて住宅の購入を考えている方は多いのではないでしょうか。



こちらでは、50歳から住宅ローンを組んで家を購入するための3つの方法を解説します!
- 定年退職時に完済できる金額を借りる
- リバースモーゲージ型住宅ローンを活用する
- 親子リレーローンで返済する
50歳を超えてから住宅ローンを組むことは、完済年齢が高くなるため簡単ではありません。ぜひこちらで紹介する方法を検討してみてください。
1. 定年退職時に完済できる金額を借りる
多くの金融機関では、住宅ローンの完済年齢は80歳です。基本的には、80歳までに完済できる返済計画でローンを組む必要があります。
また、50歳を超えてからは繰り上げ返済できる可能性が低いため、定年退職までに支払いが終わる金額で借り入れましょう。



退職金や年金からの住宅ローンの返済は、老後の生活に悪影響を与えるため避けたほうが安心ですよ!
定年退職までに効率的に返済する方法を知りたい方は、すーさんに相談するのがおすすめです!家づくりに関するお悩みを5,000件以上解決してきた経験を活かし、どのようなことでもアドバイスできます。
LINEで無料相談できるので、お気軽にご連絡ください!
\ ノープランでOK /
2. リバースモーゲージ型住宅ローンを活用する
リバースモーゲージ型住宅ローンとは、毎月利息だけを支払い、名義人が死亡した後に自宅を売却して元本を完済する方法です。
リバースモーゲージ型住宅ローンを利用できる年齢は金融機関によって異なりますが、50〜60歳程度が一般的です。



保証人は不要ですが、相続人の同意書が必要になります!
また変動金利での契約になるため、毎月の支払い額が変動する点がデメリットです。
3. 親子リレーローンで返済する
子どもが同居する場合は、親子2代で返済する計画を立てる方法があります。
たとえば、65歳までは自身が支払い、それ以降の返済は子どもが引き継ぐ形で返済計画を立てます。



親子間でトラブルにならないように、返済方法についてよく相談しておくことが大切ですね!
家を買うべきでない人の3つの特徴
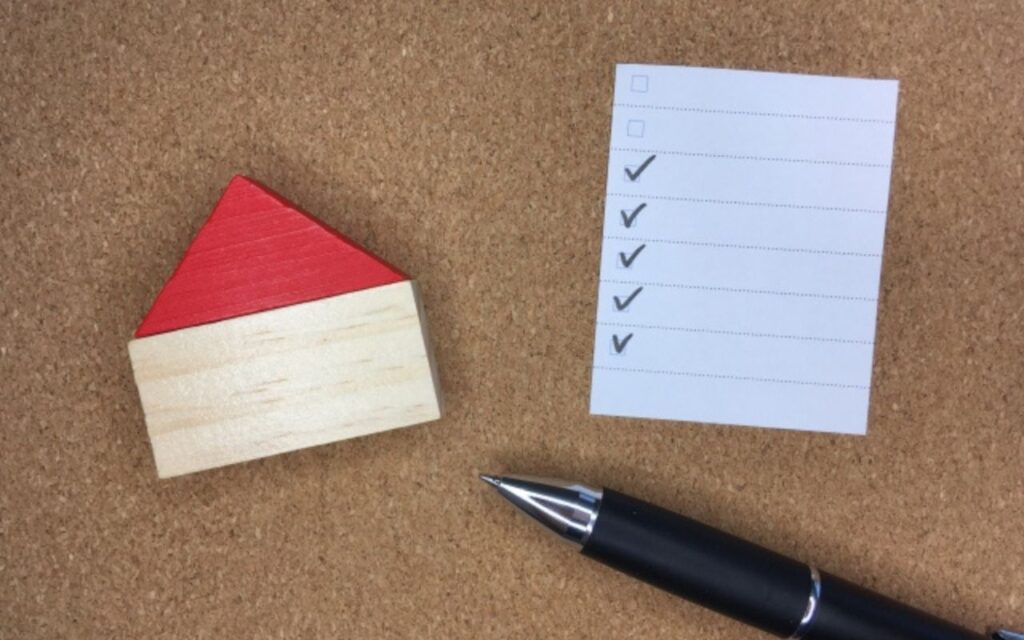
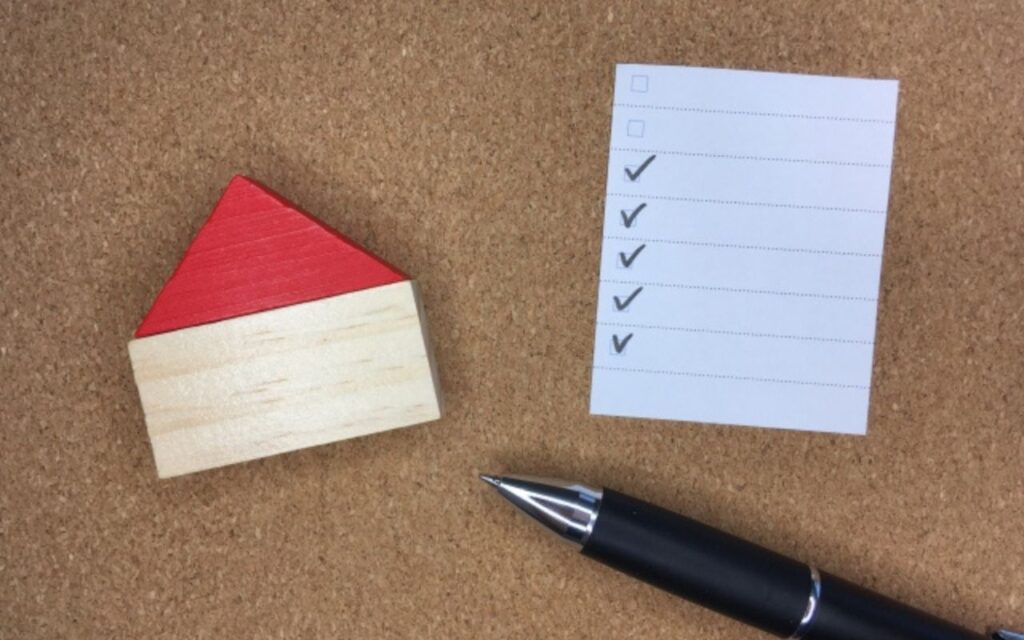
家を買うべきでない人の特徴を紹介します。
- 多額のローンを組むことに負担を感じる人
- 転勤や親の介護で家を空ける可能性がある人
- 利便性や自分に合った街に住みたい人
一つずつ見ていきましょう。
1. 多額のローンを組むことに負担を感じる人
住宅購入資金は高額であるため、住宅ローンを組む人が多いでしょう。



住宅ローンは返済期間が長く、多額です!
数千万円などの高額の返済を長期間支払い続けることを負担に感じる方は、家を購入しない方がいいでしょう。
2. 転勤や親の介護で家を空ける可能性がある人
将来的に転勤や介護で家を空ける可能性がある方は、家を購入しない方がいいでしょう。購入した自宅に住めない場合には賃貸に出すこともできますが、手間がかかってしまいます。



転勤する可能性がある方や実家が遠い方は住宅購入前にしっかりと検討しましょう。
3. 利便性や自分に合った街に住みたい人
変化する生活スタイルに合わせて、利便性や自分に合った街に住みたい方は家を買わないほうがいいでしょう。



頻繁に家を住み替えたい方には購入しないほうがいいですね!
自分のライフスタイルに合った家にその都度変えたい方は、賃貸住宅を選ぶのがおすすめです。
家が欲しいと思ったらタイミングや予算から検討を始めましょう


新築で家を建てる場合には、資金計画や家の設計など検討しなければならないことが多くあります。
現実的には、ハウスメーカーの営業担当の方からアドバイスを受けながら、家づくりを進めることになります。しかし、どのハウスメーカーに相談すれば良いかわからない方が大半でしょう。
家づくりの相談は、まず「すーさんの相談窓口」にお問い合わせください。



15年間ハウスメーカーの営業マンとして家づくりに携わってきた僕が、中立的な立場で適切なハウスメーカーを紹介します!
家づくりのことであればどのようなことでもアドバイスできるので、ぜひお気軽にご相談ください。